
Warner-Pioner Corpration,Japan
L’opéra Fragile (1981)
Warner-Pioner Corpration,Japan
Venèzia (1984)
CBS/SONY INC TOKYO JAPAN
加藤和彦の闇
夢は曠野を 駆けめぐる Vodka
ピアノを苛立たせる Vodka
情熱と絶望の 間をぬって 人は踊る
運命の舞台裏で 糸を引くのは 見えない手
人生の舞台裏で 糸を引くには 見えない手
これは1981年に発表した加藤和彦のアルバム「Belle Excentrique」の「ディアギレフの見えない手(Diaghilev, L’homme-Orchestre)」からの1節。加藤はこの安井かずみの歌詞をビロードのような艶やかで肉厚なメロディーに乗せて歌い上げた。ぼくは「帰ってきたヨッパライ」を同時代の歌として耳にしていたが、加藤和彦の音楽を一番熱心に聴いていたのが、このアルバムをはさむ上の3枚が発表された時期だった。一番上は「うたかたのオペラ(L’opéra Fragile)」(1980年)。続く「Belle Excentrique」と、一番下が「Venèzia」(1984年)。3作ともDrumsは初期サディスティック・ミカ・バンドのメンバーでもあった高橋幸宏が担当し、他の2作には細野晴臣、坂本龍一、そして矢野顕子といった後の「チームYMO」の面々がバックを手堅くサポートしている。ジャケットデザインも「L’opéra Fragile」は奥村鞍正さん、後の2枚は渡邊かをるさん。そして妖艶なPaintingは画家の金子国義さんが担当している。これらアルバムからは80年代特有のハレの空気感が今も濃厚に伝わってくる。
3作はともに当時加藤とは私生活のパートナーでもあった作詞家・安井かずみとの共作によるものだ。これまで数多くのヒット曲をてがけてきた彼女がこの時期から仕事を加藤との共作作業に絞って、ほんとうに自分が書きたかったものだけを表現しようとしていたことを先日見たTVのアーカイヴ番組でぼくは知った。そこであらためて聴きなおしてみると、まるでミュージシャン加藤和彦がシャーマンとなって安井かずみをこの世界に再来させようとしているかのような錯覚にとらわれる。ほどなく訪れる死別によって彼らの幸福な並走に終止符が打たれるのだが、それを期にやがてぼくの中でも彼らの音楽への興味は急速に薄れていってしまった。ぼくは加藤和彦の音楽に包まれた安井かずみを見つめていたのかもしれない。
若い頃通ったことのある美術研究所に、かつて安井かずみも在席していた時期があり、当時の話を所長から何度か聞かされていた。彼女はほんとうに典型的な都会のお嬢さんだったようで、田舎育ちのぼくとは違う世界で育った人なんだと話を聞きながら思ったものだった。
この3作におさめられている曲の舞台も多くはヨーロッパやニューヨークの街々。映画のワンシーンのように異国を背景に男女の心の機微が描かれている。加藤和彦はスーツを仕立てるためだけにわざわざロンドンまで出向いたり、良いと認めたものには金に糸目をつけなかったそうだから、嗜好面においてもこの二人は深く共鳴しあっていたのだろう。行間に漂う何ともゴージャスで洗練された高尚な美意識は時として鼻につくこともあったけれど、それでもぼくが聴き続けていたのは詞の背後に忍び込む諦観とか自身を遠景に置いてみる覚めた視線、そして屈折した心情を変幻自在にデフォルメしながら包み込む練り込まれたサウンドに魅せられたからなんだと思う。そこには60年代から世界中で生み出されたポップスのエッセンスが巧みに引用されていた。即座に思い浮かぶのがアメリカ生まれのミュージシャン、ライ・クーダー。彼は学者のような緻密な分析力とあくなき探求心で世界中から素晴らしい音楽を採取し、再構築してみせるぼくの大好きなミュージシャンである。この時期の加藤和彦は和製ライ・クーダーといってもいいほどのパッションとプロフェッショナルな技を繰り出し、希有なパートナーと共に屈折した心情を音楽の中に封じ込めてみせた。
ところでぼくは、加藤和彦の音楽は本質的にはゴージャスな砂糖菓子の世界だと思っている。ドノバンに傾倒してトノバンと呼ばれていた時代の「家をつくるなら」や「あの素晴らしい愛をもう一度」、「白い色は恋人の色」などといった初期の代表曲は彼ならではの柔和な穏やかさにあふれていて、そこにわずかな含羞も含まれているのが何ともほほ笑ましい。人はリアルな世界に疲れた時、そっと砂糖菓子が欲しくなることがある。だからぼくは決して揶揄する意図があって彼の音楽を砂糖菓子と言っているのではない。本当に上質な砂糖菓子だと思っているのだ。
そしてもうひとつの側面はアジアの音楽家としてのウエットな一面。詩人サトウ・ハチローの詞をもとにした「悲しくてやりきれない」や朴世永・高宗漢の詞曲「イムジン河」の再構築、そして辞世歌「感謝」などからは、アジアンチックな郷愁漂わせる京都人としてのもう一人の加藤和彦が現われてくる。砂糖菓子の背後に潜む静謐な深い闇。常に誰かに自身を添わせ、重ね合わせて表現を模索してきた音楽家が闇の中にひっそりと佇んでいる。
偶然にも自死の前日、隣りに彼が立っていた一瞬があった。10月15日午後3時30分頃、用あって六本木ミッドタウンに車を乗り入れ、ぼくはビル内のディーン&デルーカ・ショップでコーヒーを飲みながら一休みしていた。ふと左隣りから季節はずれのマドラスチェックのハーフパンツ、そしてカラフルなストライプ・サンダルを履いた長身の人物が視界に入ってきた。頼りなげに細く伸びた白い足が印象的だった。ちらっと斜め後ろから眺めると金色の短い髪だった。ずいぶん派手な老いた外国人もこんな場所には来るんだなぁと思ってそれきり視線を外してしまった。しばらくして向かいに座っていた連れからそれが加藤和彦だったことを知らされた。彼はその時一人で赤かぶのマリネをワンカップ買い求めていたそうだ。もしそれが最後の晩餐のメニューだったとしたら、彼の人生に比してそれはあまりにも質素でつつましいものではないか。いや、だからこそ、そこにはぼくなどの計り知ることのできない必然の計らいがあったのかもしれない。ディアギレフの見えない手によって…。

浅葉克巳さん親子
秋以降、政権についた民主党の関連報道が倍増している。これまで野党として露出が少なかった民主党議員たちの動向は、表舞台に移動してから連日スポットライトを浴び続けている。
とりあえずアメリカに倣って、「変化」を選択した我が国の世論。そしていまは期待と不安の入り交じる政権移行期間。政治舞台の明転は移ろいやすい人心の目にはしばらく新鮮に映るだろうが、大切なことは政治を安易に劇場化しないことだ。ほんとうに変化を選択したのかと短兵急に結論を出し急ぎせずに、しばし注視してみる忍耐力が必要とされているんだと思う。政治は生活に直結しているから当然無関心ではいられないが、ぼくは基本的に自分のことをノンポリティカルだと思っている。つまり特定の党派に属することを拒否する人々の一人であって、棄権せずにその都度支持する政党や政治家を選択している平均的な無党派層なのである。
それにしてもかつての与党の凋落ぶりには目を覆いたくなる。良質な保守、そして保守への回帰なんて何言ってんのって感じで、一体何を保ち守ろうというのか。こんな手垢のついた政治言葉にもういいかげんぼくらはうんざりしているし「一緒にやろうぜ!」と気勢をあげられても長期ビジョンそのものがきちんと描けていないのだから、何とも寒々しい気持ちになってしまう。保守と革新の対立軸なんて前世紀末に消失してしまったのに、保守へ回帰すると言われても、そんなの国を担ってきたと思い込んでいる政治家たちの本流意識を主張するお題目にしか聞こえてこない。このように組織の人材が枯渇すると、その危うさはある日突然非情な事実として顕在化する。結末は分かっているのにどうすることもできず、空ろな面持ちで進むことしかできない。これは権力に吸引された末、疲弊してしまった構造体に襲いかかり、これまで幾度となく繰り返されてきた歴史の必然でもある。いつか来るべき山を迎えるためのいまが谷越えと頭をリセットし、精進するしかないですね。
さて、そんなノンポリ・デザイナーがずっと気になっていたのが政権デビューした民主党のシンボルマーク。国旗2枚の各パーツを切断し、縫い合わせて前首相に批判され話題となったあのシンボルマークのことです。じっと眺めていると達磨さんにも見えてくるが、上下に交差する赤い円は無限大「∞」を意味しているそうだ。そして下の円の輪郭がガチガチしているのは、新しいものを生み出していく様子を示していて、まだ成長途中なので輪郭がはっきりしていないということなのだと、民主党議員・よこやま博幸さんのサイトでは説明されている。また、水平線の海面から頭を出した太陽のイメージであるという説もある。つまり真ん中の白い部分がさざ波で、下の円が歪んでいるのは海面に映った太陽だからという「日はまた昇る」のイメージ。じゃあ落日もありうるぜと意地悪なツッコミが入りそうだけど、日本の夜明けを表現しているというところだろうか。作者はArt Directionがグラフィックデザイナーの浅葉克己さん、Designが子息の浅葉弾さん。なるほどと思いつつ、ぼくはまた別な解釈をしていて、上は目指すべき国のイメージ。そして下はまだ粗削りな政党ではあるけれど、目指すべき正円に重なるべく日々研鑽を積んでいるという意志の視覚表現であるとも考えてみた。ただこの解釈の場合、2つの円が完全に重なってしまうという事態はこれまた空恐ろしい。
ま、解釈はともあれ、ずっと気になっていたのはシンボルの下の円の造形についてだ。なんとも下の円の形状は受け入れがたいものがある。作者はこう反論するかもしれない。この造形は手だれておらず素人くさいと言われても、粗削りな理想を追い求める純真さを象徴しているのだと。そういう意味を汲んだとしても、あの形状には決定的に破綻していると直感させてしまうような稚拙感が拭えない。事実ネットでも下の円についての拒否反応は決して少なくないようだ。
そこでお節介もほどほどにと言われそうだが、勝手にリ・デザイン。(ごめんなさい、浅葉さん!!)一番上がオリジナル。下はおせっかいプランの数々なのだが、民主党は寄り合い所帯なんだから、やっぱり輪郭はデコボコしてしまう。でも角はほどよくとれていて、各パーツはリベラルに連結をしている。中段のいろいろなプランのように、その時の党内事情を反映させて微妙に起伏やデコボコの数が変化するなんていうのもいいかもしれない。
シンボルは不変不動。変化してしまったらシンボルじゃなくなってしまう、これが長い間デザイン界での常識だった。でも、SONYのCIやテレビ朝日のVIのように、ロゴ自体をアプリケーションとして機能させ、動きや色を環境によってフレキシブルに変化させるデザインも続々と誕生している。これらSONYやテレビ朝日のロゴを制作担当したのは、社会心理学などをバックボーンとした方法論で注目を浴びてきたイギリスのデザイングループTOMATO。まだSONYのCIが本格的に展開される前、デザイン会議でTOMATOのこのプレゼンテーションを見る機会があった。SONYのロゴがTV画面に現われてくる時の動きや色が、放映される国によって、その日の気候によって、また放映地域の人工密度などによって、微妙にプログラムコントロールされていくというアイデアだ。なるほど、ロゴをグラフィカルでなく社会心理学的に考察すると、ビジュアルをスタイルに還元させないこんなアプローチも可能になるんだと感心したものだった。
そこで、今の民主党はこんな形であると我々は考えています、と1年ごと年頭にサイトでシンボルマークに反映させてみたらどうだろう。時代感覚の多層化したチャンネルに対応して、政治にも柔軟なコミュニケーション能力が求められているのだと思う。現行ロゴを比較的忠実にスライドしたプランが最下段の左。右は今の党の印象に一番近いとぼくが感じるプランである。

つげ義春の世界
9月15日の深夜、NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀・闘いの螺旋、いまだ終わらず〜漫画家・井上雄彦」をチラ見していたら、つい引き込まれて最後まで見てしまった。吉川英治の小説『宮本武蔵』をもとにした青年漫画『バカボンド(放浪の人)』を執筆する漫画家・井上雄彦の日常に密着した取材番組だった。1998年からモーニングに連載が開始されたこの作品は、なんと10年以上も続く大長編連載漫画だ。どこかでうっすらとこの『バカボンド』を目にした記憶はあるが一度もきちんと読んだことはない。
井上雄彦という人は24時間制作に没頭する日々を切れ目なく送っているにもかかわらず、一点でしっかりと実生活に根を張り、誠実さというか堅実さを漂わせている。腕の立つ職人のように気負いや浮ついたところが感じられない。一口に漫画家といってもそれはいろんな人がいるわけで、度々TVに登場しては気の利いたコメントを量産する小利口な漫画家などを見るにつけ、ぼくはこういう職人タイプには無条件で好感をもってしまう。鹿児島県出身の42歳。幼年期には水島新司の『ドカベン』が好きだったそうだが、鋭い画風はさいとう たかをの系譜に連なるような気がする。なにしろ素晴らしく絵がうまい。台詞がなくてもわずかな表情だけで豊かな表現力を発揮できるタイプの漫画家だと思う。
ところでずいぶん乱暴な仕分けだけど、少年を傾向別に野球少年と漫画少年に分けるとしたら、ぼくは間違いなく後者だった。しかし、運動神経もないのに背番号3のついたユニフォーム姿の写真が残っているくらいだから、野球も大好きなハイブリット少年だったとも言える。親の話では、物心ついた頃から身の周りにある紙切れに少しでも白いスペースを見つけると何かしら描きつけていたそうだ。自作の落書きが整理箱に入りきらないで困ったという記憶もある。小学生になれば『少年』や『少年画報』といった月刊誌では飽き足らず、近所の貸し本屋に入り浸るようになる。小さな駅の脇に隠れるようにその店はあって、たしかぼくと同年配の双子姉妹がいた。その家にはまったく男性の気配がなかったから、もしかしたら母子家庭だったのかもしれない。ちょっと暗くてひんやりとした店内に通っては、当時お気に入りだった辰巳ヨシヒロの陰鬱でシリアスな社会派漫画なんかを抜き出しては片っ端から読み漁っていた。
やがて漫画が動き出す。ウォルト・ディズニーのアニメーション映画を劇場で初めて観た時の驚きは今でもはっきりと覚えている。それまで見た日本のアニメーションといえば、ぎこちなく動きまわるキャラクターたちばかり。いかにも作り物っぽい印象がつきまとっていてあまりイケてなかったのに、このアメリカのキャラクターたちはどうだろう。見たことないくらい動きはなめらかでリアルだし、表情豊かでファンタスティック。でも感動もそこまでだった。どんなに巧妙な仕上りでも、それはどこまでいっても作りものの世界のまま。そんなこといえば、あらゆる表現物は作りものの世界に過ぎないともいえるわけだが、そっと心に沁み込んできて、作りものでないリアルな感情と重なり合うことは有りうるわけで、そんな表現物を漫画を通じてぼくは探し求めていた。
日本漫画史の神様みたいな手塚治虫は確かに大天才だった。あれだけ漫画表現に人生のすべてを捧げた生き方を貫徹した人はそういないし、残された作品群もその生き方と才能に見合うフロンティア・スピリットの輝きを湛えたものばかりだ。そんな濃密でハイレベルな作品をたくさんつくってくれたのに、ぼくはディズニー同様に夢中になることができなかった。生来、手塚治虫は生真面目で誠実な人だったのだろう。だから作品がどんなにシリアスで革新的なものであっても、結局は理想主義的な印象がつきまとうものだから、何となく物足りなさを感じていた。その反動で、早く良い子を卒業したかったぼくは水木しげるや白土三平に夢中になり、二十歳過ぎには、これでいいのだ!の赤塚不二夫やハレンチ学園の永井豪も登場してきたので、この漫画の国で少しも淋しいと思ったことはなかったのだ。
秋政権についた民主党の反対でさっそく凍結されてしまったが、いろんな漫画を網羅してストックしていこうという「アニメの殿堂」と呼ばれる国立メディア芸術総合センター構想にまつわる騒動ついて、漫画家たちはどう感じているんだろう。応援・支援は結構だけど、本音は「ほっといて欲しい」というところじゃないだろうか。ずっと漫画になんか目もくれなかった政治家たちが、海外人気を受けて手の平を返したように「世界に誇る日本アニメ」なんて持ち上げても「今さら、そりゃないぜ、おじさん」と多くの人がうさん臭さを嗅ぎ取っているようだ。およそサブカルチャーの原動力にはエログロナンセンスもたっぷりと吸い込んだ、良識派が眉をひそめるようなパワーがおおいに含まれるわけだし、そこのところを去勢されて殿堂入りしても魂を抜かれた仏になってしまう。ハコモノありきは論外だけど、邪魔しないことが最良の支援という極端な考え方だってあるわけだし、公平論で武装されたパブリックの中にサブカルチャーを再構成することの難しさや危うさは強く認識しておく必要があると思う。
多くの日本人は子どもの頃からいろんな漫画に囲まれて成長する。そしてやがて大半の漫画少年たちは漫画に愛着を抱きつつも、結局漫画家になることもなく、それぞれの大人になっていく。ぼくも漫画を含めて映画や小説、そして音楽とジグザグ寄り道しながら年を重ねてデザイナーとなり、いつしかまったく漫画を手にとることもなくなってしまった。
ただひとつの例外は、つげ義春だった。この漫画家だけは避けて通ることができなかった。1970年代前半に活躍したガロ系漫画家の元祖的存在といわれるこの作家をいたずらに偶像化する気はさらさらないが、決して多数派に支持されることはないだろう『ねじ式』や『ゲンセンカン主人』といった作品には抗いがたい魅力を感じてしまった。小学校卒業後、メッキ工やそば屋の出前持ちなどを経て貸し本作家としての活動を開始したという来歴や、強度な赤面恐怖症に悩まされるような神経症的特質も作品に透けて見えている。温泉めぐりの旅や夢の採集をテーマとした作品も多い。1976年に講談社から刊行された文庫『義男の青春」のあとがきで故・石子順造氏は次のように的確につげマンガを評している。「いいかえれば、それは、沈黙の言葉なのである。沈黙について説明した言葉ではない。語れば語るほど、語れないことがあらわれてくるといった表現。それが、つげの作品ではなかろうか。」
表舞台では希望にあふれたドリーミーなドラマが繰り広げられている。しかし絶望あっての希望なわけで、舞台裏では合わせ鏡のようにシュールで不条理な出来事が沸々と沸き上がっている。それら表裏丸ごとの舞台こそが、ぼくらの生きている世界そのものなのだから、つげ義春ほどその事実を深く抉り出し、見事にディズニーの世界を反転して示してくれた作家をぼくは知らない。
*写真上は晶文社刊『必殺するめ固め・つげ義春漫画集』のカバーで、ブックデザインはぼくの敬愛する平野甲賀氏だ。表題作の舞台は、村じゅうの家が温泉でつながっている或るかくれ里。夫婦で夕涼みしていたら、謎の元プロレスラー男に妻が手ごめにされた上、必殺するめ固めの技をかけられて、歩くことも口をきくこともできなくなってしまった男の苦悩と悲哀が描かれている。元来寡作な作家であったが、この作品を発表した1979年以降、進行したノイローゼの治療もあって休筆状態となり、1987年の『別離』を最後に現在までほぼ沈黙を続けている。写真下は1968年に発表されたガロ時代の代表作『ねじ式』の巻頭頁。22頁にわたる悪夢のようなオブセッション(脅迫観念)がシュールにパッチワークされている。
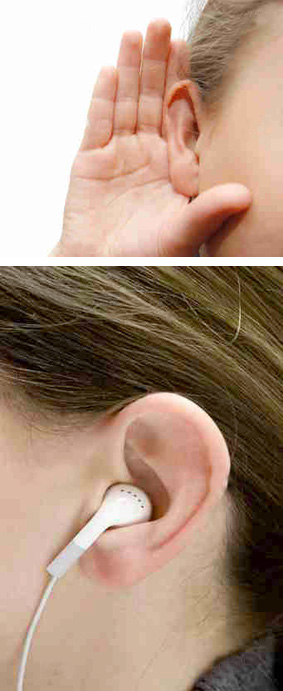
電子書籍の未来
以前「電子書籍」のことに少し触れたことがある。どうやらこのところアメリカではその電子書籍の市場が急速に拡大しているようだ。この2年ですでに5倍の規模に成長したという記事を目にした。それでもまだ全書籍の1%強にすぎないが、書籍の売り上げは音楽の3倍もある大きな市場なので裾野は想像以上に広いと期待度も高い。
このアメリカにおける急成長のきっかけはアマゾン「キンドル」のヒットだった。さらにその後ソニーも参入してソフトや端末を投入。伸びしろの大きい市場に向けて果敢に攻め込んでいる。音楽がネット配信へと大きく流れを変えた経緯から、どうやらアマゾンとソニーの両社は書籍の電子化が進むのは間違いないと読んでいるのだろう。さらにアメリカ最大の書店大手バーンズ&ノーブルも最近ネット販売を開始したというから、どうやらひと足先にアメリカが本格的な電子書籍化時代に入りつつあるのは間違いない。
ところで先日、朝日新聞の「本の舞台裏」という連載コラムに興味深い記事をみつけた。ジュンク堂池袋本店が開催した「耳から読む・大活字で読むCDブック大活字フェア」の中で本の内容を録音した音訳CD(オーデオブック)を紹介していた。取り上げられていたのはボランティア団体が出版社の委託を受けて制作したもので、単なる朗読にとどまらず図表なども正確に読み上げるのが特徴となっている。これまでの音訳は全国におよそ30万人いるとも言われる視覚障害者を想定したものが多かった。しかし高齢化により需要は確実に広がりつつあるし、ラジオ視聴者には高齢者も多いときく。それに団塊世代だって控えている。この団体ではおよそ60人のボランティアによって単行本なら3週間から2ヶ月、雑誌「週間金曜日」は発売翌週の火曜日には利用者の手元に届れられるそうだ。音訳CDの存在がもっと世間に広まって販売する出版社や取り扱う書店が各地に増えてくれることをこのボランティア団体の代表者は願っているようだが、まだまだタイトル数は限定され、当然価格も通常本より高い。残念ながら現時点では「耳から本を読む」こうした試みは過渡的な実験段階にとどまっていると言わざるを得ない。「電子書籍」や「音訳CD」は、はたして書籍の発展型メディアとなるのか、それとも単なるIT時代のあだ花で終わるのか、着地点はいまだ霧の中である。
似たような試みは過去にもあった。ぼくの書棚に収まる角川書店刊の「ランボー詩集」(金子光晴訳)と大門出版刊の「シリーズ私の講義・西脇順三郎集」の2冊には巻末にソノシートが納められている。今となっては懐かしのソノシートなのだが、当時はバリバリの最先端メディアだった。こんな紙みたいに薄いフィルムから音が出てくることにワクワクしていたのだからほほ笑ましい。どちらも昭和42年(1967)発行で、どうやら高校生になった年に購入したものらしい。そういえば「ランボー詩集」のソノシートは何度も聴いた記憶がある。叙情的なBGMをバックに「いちばん高い塔の歌」の「束縛されて手も足もでないうつろな青春。」なんて一節を思い入れたっぷりに芥川比呂志が朗読するのだが、それはそれで文芸的なアプローチだとは思うけどやはり作品とはまったく別なもの。曲解させる危険も孕む試みでもあった。
音訳CDの可能性は、こうした試みの先には決して見えてこないような気がする。器にどう盛りつけるかでなく、どんな風にも盛りつけることを可能にする「器そのものの実現性」が問われているのだと思う。
先日、キュレーターの長谷川祐子さんと大手出版社の編集者を交えて立ち話していた際、長谷川さんが音訳CDのことを話し出した。外国人の友人が(たぶんiPodで)通勤中にキンドルの音訳された研究書を聴いているという話。目を酷使しすぎた時代から聴覚で視覚をカバーする時代に入るかもしれないから出版社でも検討してみる価値があると編集者に助言していたのだが、ぼくはあの「ランボー詩集」のことを思い出し、文学作品から専門書や研究書までカバーするためにはあまり感情移入されていない透明感のある(機械的?)音声の方が望ましいこと、案外ここがポイントなのかもしれないとその時思った。
現実的には音声による入力が一番手っ取り早い方法だろう。それを素材にしてフィルタリングし、音声から個性を除去していくような工夫がほしい。リスナーは多様だ。だからその多様性を個別に反映できる柔軟性がとても重要になってくる。例えばその時の気分にあわせて音声のスピードコントロールができたり、女性や男性に声質を切り替えられたり、あるいは性別を固定しない中性的なボイスがほしいということもあるかもしれない。もちろんBGMなんかもお好みでバックに貼り付けられる。
リスナーの多様性に応じてカスタマイズできるシステムの実現は決して夢物語ではないだろう。こうして人間の生理に違和感なくフィットできるシステムやテクノロジーが実現されたら、霧なんて案外あっという間に晴れてしまい、「電子書籍」や「音訳CD」がしっかりと大地に根をおろしている光景をぼくらは目撃することになるのかもしれない。

SHIRT
みんな自分がわからない
その時自分がどうしてそんな行動をとってしまったのか、後で思い返してもよくわからない、そんな経験をぼく(ぼくら?)は時々することがある。ずいぶん昔に出版されたビートたけしの「みんな自分がわからない」という啓発本がある。内容的にはあまり共感できる代物ではなかったが、このタイトルだけはたしかに真理を突いていた。
日常ぼくらの行動を制御している「意識」は、いわば周囲の風景を写しだす水面のようなもので、実はその下には底知れぬ深さを湛えた「無意識」と呼ばれる領域が潜んでいる。オーストリアの精神分析学者、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)は夢を研究する過程でこの「無意識」を発見したと言われているが、「無意識」とはその名の通り、心のなかの「意識でない」領域を示す。もっと簡単に言うと、「無意識」は「意識」よりも大きな存在で人間の行動のほとんどはこの「無意識」の欲望がもとになっている。しかも人間はこの「無意識」を自覚することはできない。つまり自分のなかの知らない自分、それが「無意識」というわけだ。
冒険という言葉が死語となってしまった感もあるほど、ほぼ世界中のどんな地域にも移動できる手段を今や人間は手にしている。しかし自身のなかには、いまだ解明されない膨大な未開の大陸が残されたままというのは何とも皮肉な話である。その大陸の奥深くでは片時も休むことなく、常識や社会のルールなどに拘束されることのない野生が荒々しくうごめき、さらにその奥に穿たれた穴は自然そのものと直結しているのかもしれない。宮沢賢治「春と修羅」の「序」で語り出されているあの有名な一節「わたくしといふ現象は 仮定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です (あらゆる透明な幽霊の複合体)…以下略)の透明な幽霊たちは、おそらくこの「無意識」の大陸を住み処としているに違いない。
ところで数年前、ぼくは青山にあるコム・デ・ギャルソンのショップでヴィクトル・ヴァザルリ(Victor Vasarely)の抽象画を連想させる、うねるドッツパターンのシャツを購入した。ジッパーが2本あってなかなかにアヴァンギャルドなこのシャツは、その後袖を通す機会もなくクローゼットのなかで眠ることになる。また衝動買いをしてしまったなと軽く反省しつつずっと封印したまま過ごしてきたが、この初夏のある催しに出かける際に「そうだ、これを着ていこう!」と思い立った。
その催しとは多摩美術大学のIAA(芸術人類学研究所)が主催するシンポジウム「アール・イマキュレ—希望の原理—」と同時開催の展覧会。IAAは数年前からダウン症の人たちのためのプライベート・アトリエとして活動していたアトリエ・エレマン・プレザンと協働して、ダウン症の人たちがつくりだす芸術作品を通じて、彼らの感性と心のあり方を考察し、そしてサポートする活動を継続してきた。初回のシンポジウムは2007年に東京都現代美術館で、そして今年はIAAの新たな活動拠点となった四谷CCAAアートプラザで2回目となる展覧会とシンポジウムが開催されることになったのだ。ぼくはこのダウンズ・タウン・プロジェクトと名付けられた活動の立ち上げ段階から、IAA所長である中沢新一さんに誘われてデザイナーとしてかかわってきた。今回もフライヤーとブックレットのデザインを担当していた経緯もあったので、前回出席できなかったシンポジウムを今度こそ見学してみようと、クローゼットに眠る草間弥生の作品みたいなシャツを着込んで出かけて行くことにした。
蒸し暑い曇り空の下、大勢の人々が会場となった四谷ひろばに集っていた。それまで仕事を通じてダウン症の人たちの作品には数多く触れていたつもりだったが、その日初めて原画と対面して驚いた。天真爛漫な児童画に近いものではという予想に反して、その技法は相当に本格的なものだった。美術の専門教育などとは無縁の彼らは一体どこでこの技法を体得したのだろうか。アトリエはできるかぎり自由な創作の場を提供することに心を砕き、表現に介入することは極力避けているそうだから、これは「この世に出現した」としかいいようのない現象といえるだろう。特に多くの人々が一様に賛嘆する色彩感覚はほんとうに素晴らしい。言葉にならない彼らの言葉が彩りをまとって深く、強く心に滲み入ってくる。シンポジウムで、まず壇上に上がったアトリエ・エレマン・プレザン東京代表の佐藤よし子さんは、ご両親が三重で始めたこの活動に幼少期から寄り添い、もっとも濃密にダウン症の彼らと日常的に触れ合ってきた人である。いつものおっとりとした口調でアトリエの活動を来場者たちに丁寧に伝える姿は、何か守護する女神を連想させた。
伝統的な訓練を受けることもなく、既成概念にとらわれることのない作品は一般的にアウトサーダーアートと呼ばれる。この呼び名はジャン・デュ・ビュッフェの提唱したアール・ブリュット(Art Brut=生の芸術)を英訳したものだが、ダウン症の人たちの作品はアール・ブリュットの表現とその境を接してはいるものの何かが決定的に異なるのではないかという観点から、IAAとエレマン・プレザンはそれをアール・イマキュレ(Art Immaculé=無垢の芸術)と命名した。
「アール・ブリュット」と「アール・イマキュレ」。
当日の講演では出演者の臨床心理学者、河合俊雄さんと本展のキュレーター、長谷川祐子さんが、このふたつの特性の違いについてそれぞれの専門領域から興味深い考察をされていた。
そして最後に引き継いだ中沢新一さんがさらに鋭くフォーカスして特質の相違点を明快に来場者に差し出してくれた。冒頭、中沢さんはアール・イマキュレにはほとんどみられることのないアール・ブリュットの特質のひとつに「目」の存在をあげた。平面的に形成されている現実の世界に穿たれた穴(または空洞)は隠れた心の本質を表している。「外側に表われている自分だけが自分なのではないという心の叫び」「自分の心が平面化(あるいは平準化)されてしまうことへの抵抗感や攻撃性が「目」の表現を通じて伝わってくる。配付資料には「アール・ブリュット」の特徴的な作品がピックアップされている。例えば「目」で描かれたマンダラのようなアドルフ・ヴェルフリの作品や、伊藤若冲の「動植綵絵 薔薇小禽図」(中沢さんはここに描かれているおびただしい薔薇の花は「目」にほかならないと指摘している)を見ると、反復される平準化に抵抗する心の叫びがひしひしと伝わってくる。
そして会場でこの配付資料を眺めながら、ぼくはやっと思い当たるのだった。コム・デ・ギャルソンのショップで出会った反復する「目」のドッツデザインは、実はその時ぼくの「無意識」が欲望していた形でもあったのだ。こうして数年も経てから、もう一人の自分に出会うこともある。
では「アール・イマキュレ」にしかみられない特質とは?
「イマキュレ=無垢」という言葉は宗教語に由来するそうだが、もうひとつ「アール・アンジェリック=天使的な芸術)」という候補名があったことでも明らかなように、ほとんど「目」を描くことはないダウン症の人たちは、その作品の中に明るい光ややわらかいベールで包まれたような不思議な空間をつくりだす。天使という概念はあらゆる中間的なものの象徴だ。人間でもなく神でもなく、この世でもなくあの世でもない。静止したり固定することもなく、途切れることなく絶えず微細な振動を続ける中間的な空間。
中沢さんたちはここに人類の未来のビジョンを描くうえでの大きな手がかりを感じとっている。当日配布されたブックレットのforewordの文末でこのように記している。「…それから2年、ぼくたちは少しだけ、着実に前に進んだ。アール・イマキュレを現実世界に投げ込んで、その中にあっても変質することのない、ほんものの強さを持続させるにはどうしたらよいのか、現代でも無垢であることは希望をともす原理の燈台であり続けることができるのか。ぼくたちは試行錯誤しながら手さぐりでその答えを探し出そうとしてきた。そういう探求を続けているうちに、ぼくたちは知らない間に、自分たちが少しだけ前進していることに気がついた、アール・イマキュレは幻想ではない。それは現実世界の中で、生き抜いていく力と希望の源泉のひとつであることを、ぼくたちはあらためて見出しつつある。」
ぼくは今回のフライヤー・カバーに(そしてこの催しのシンボリックなイメージとして)1点の絵画作品を選んだ。「佐久間さん」(モデルとなった佐久間さんは佐藤よし子さんのパートナーで彼女とともにアトリエの運営にたずさわっている)というタイトルのつけられたこの作品の作者は岡田伸次さんという27歳になるダウン症の若者。シンポジウムが終了した後、関係者の一人がぼくを彼に引き合わせてくれた。初対面のぼくらは向き合ってまずハイタッチ。そしてすぐに彼はぼくに抱きついてきた。ちいちゃくて柔らかい小動物を連想させるそのコロコロとした感触には、攻撃性や防御しようとする意識がまったくといっていいほど感じられない。抱擁する数秒間、ノーガードの開放感を通じて剥き出しの状態で流れ込んでくる彼の「無意識」を、その時ぼくは驚きとともに一心に受け止めていた。

Middle: Mother with two children - standing.
19th century
Below: Garment manufacturer.
19th century
生を封印する物悲しさ
完璧な引きこもりと言っていいほど毎日ぼくは仕事場にこもりっきっている。そうしないと仕事がなかなか片づいてくれないこともあるのだが、実は‘チョー’がつくほど出不精な性分によるところが多い。
しかし一区切りついて気が向くと、時折知り合いの写真屋さんまで出かけていくことがある。仕事柄の古いおつきあい。ところが、労働環境のデジタル化以降めっきりお金にならない客になってしまった。でもそんな気まぐれな突然の来訪者でも、いやな顔ひとつせず迎え入れてくれる。ぼくにとってここはいつだって峠茶屋のようなオアシスなのである。
「戸を開けると星が見える」という、何ともロマンチックで珍しい姓の店主、戸星さんと弟さんの二人が先代から引き継いだこのお店は当地で唯一ライカ(Leica)の買える専門店だ。多くのカメラ好きに愛され続け、晴れて昨年、水澤工務店施工によるギャラリー併設の新築ショップ[栄光堂]を完成させて新たな一歩を踏み出した。ショップと同時に開始されたブログからその熱中ぶりが伝わってくるように、戸星さんは最近菜園作りにはまっているらしい。新鮮な野菜を収穫すると、早朝わが家まで回り道して、そっと玄関脇に置いていってくれたりするので二重に癒されている。
さて、写真が日本に渡来した1848年からおよそ40年後、徳川最後の将軍、慶喜が明治のアマチュア・カメラマンとして写真に夢中になったことはよく知られている。最上段は、明治20年頃の狩猟姿の徳川慶喜のポートレートだが(茨城県立美術館蔵)激動の前半生と較べると、何とも道楽人生のゆるゆるモードに包まれているではないか。戦後しばらく、カメラは小さな家が一軒買えるほどの贅沢品だったそうだ。だから当時写真を撮るのは羽振りのいい旅館のご主人やお金持ちの道楽家に限られていて、写真が残されること自体、特別なことだったのだ。そんな時代のことを茶飲み話で戸星さんは楽しそうに教えてくれる。一回りほど年長の戸星さんと交わすとりとめもないそんな会話は、仕事で加熱した頭をそっとクールダウンしてくれる。思えばぼくは昔から、年上の親父さんがとても好きだった。小学生の時分、学校から帰るとすぐさま近所の銭湯に出かけては高い椅子によじ登り、番台の親父さんと向き合って将棋ばかりしていたことを思い出す。
ある日、戸星さんはふとぼくに「どうして写真を撮らないの?」と聞いてきた。そうだ、ぼくはどうして写真を撮ってこなかったのだろう。そんなこと改めて考えてみることもなかった。もちろん仕事で必要な撮影を自分ですることもあるし、グラフィックデザイナーという職業上、写真には日常的に接しているのに、(表現としての)“写真を撮る”ことをこれまで意識したことは一度もなかった。今でこそシャッターを押せば、後は至れり尽くせりのおまかせ機能がフォローしてくれて、それなりにきれいに撮影することができるが、やはりきちんとした写真を撮るためには、露出やライティング、色補正やアングル、ピントといった基本的な修練が求められる。これらは至極理論的な道理に基づく修練で、実はぼくはこれをかなり苦手とする。1、2の次に3を飛ばして4にいってしまいたくなる。早い話が面倒くさいのだ。若い頃は森山大道や中平卓馬、アラーキや篠山紀信といった写真家の作品に触れる機会はあったけど、ついに心揺さぶられることはなかった。最近話題となっている写真家の作品も知らないわけではないけど、センサーが一向に反応してくれない。
ただ10年ほど前、何度か行動を共にする機会のあった写真家・港千尋さんの装幀を担当したことを機に、あまり足を運んだことのない写真展をのぞいてみたり、港さんの著書を通じてそれまで無縁だった写真世界のことを少しだけ垣間見ることになる。なかでもアンリ・カルティエ=ブレッソン(Henri Cartier-Bresson)の仕事はとても興味深かった。トリミングの手法で写真から宿命的に発生してしまう物語性をはぎ取り、意味を宙づりにしてしまうという発明はブレッソンならではのものである。また、アンセル・アダムス(Ansel Adams)の風景写真のように、おそろしく高密度で精緻に凝着したディティールを前にすると、モノとしての写真の存在感に圧倒されてしまう。これは絵画では決して再現しえない写真ならではの真骨頂であろう。庭園美術館で見たメイプルソープ (Robert Mapplethorpe)のシルバープリントからも、古典的ともいえる写真表現の底力がひしひしと伝わってきた。長きにわたって絵画に課せられていたひとつの呪縛、つまり現実を写し取るという呪縛が、写真の発明によって解き放たれたことは間違いない。解放された絵画は、そこから精神性の奥深くまでダイビングしていく近代絵画史の旅を開始した。では、写真における精神性の旅はどこに向かっていったのか。
ぼくは、マン・レイ(Man Ray)のような絵画表現に近い実験的な試みに心踊ることもなく、デジタル技術を駆使した挑戦的な試みにもあまり関心がない。唯一魅かれるのは古い写真である。もちろんさっき撮った写真だって古い写真だ。写真はいつだって過去の記憶の1葉にすぎない。だから古い写真とは古いだけでない、そういった意味での記憶の1葉を示している。再現性のクオリティや作品としての完成度はあまり関係ない。ただ映っていればいい。それらはブレッソンのはぎ取った物語性がしっかりと沈殿しているものばかりだが、どれもこれもがどこか物悲しい。ぼくはこれが写真の本質なのではないかと密かに思っている。日常という大地を彷徨う風のようにさまざまな生はとらえどころなく、不確かでリニアなものだ。しかし写真はその流れを一瞬だけせき止めて、生を封印してみせる。ロラン・バルト(Roland Barthes)は、写真は死を写すメディアであると言ったそうだが、シャッターが押された瞬間、そこに定着された被写体に死の影が帯びることは避けられない。死に向かう「真」を「写」しとる写真という媒体。未開の人々や初めてレンズを向けられた日本人は、魂が抜き取られてしまうと抵抗感を示したそうだが、おそらくその時彼らが直感したものはこの死の影だったのではないだろうか。戦後生まれのぼくには誕生当時の写真が残されていない。初めて撮られたという3〜4歳頃の写真を眺めると、べそをかいてそれはひどい顔をしている。今でもぼんやりとその時の恐怖感が残っているほどだ。いったいぼくは何に怯えていたのだろう。上の写真は19世紀のイタリアで撮影されたスナップである。何の変哲もないただの昔のスナップ。もちろんここに映っている人々はもう誰も生きていない。だから悲しげなのではなく、生を封印する写真というメディアの本質そのものが物悲しいのだ、と眺める度にぼくは考えてしまう。
