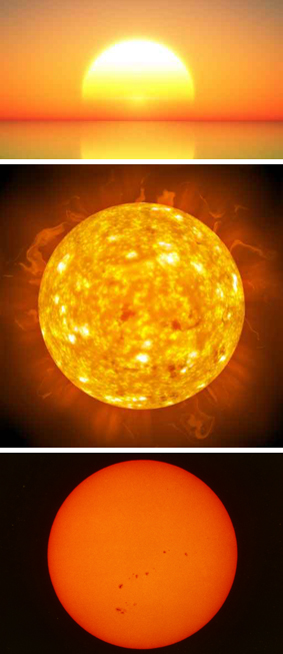
Sol : nationalgeographic
太陽光発電パネルの吸収しているもの
先日電車に乗ってぼんやりと車窓を流れる景色を眺めていたら、沿線に立ち並ぶ住宅の屋根にソーラーパネルが随分増えているのに突然気づいた。ここにも、あっ、あそこにもあるといった具合で、新築住宅を中心にそこかしこに点在していたので驚いてしまった。たしかに昨年の震災以降、人々の意識にさまざまな変化が生まれつつあることは感じていたけど、こうした光景を目の当たりにすると現実の意識変化は報道が追いつけないほどはるかに早いスピードで進んでいるのかもしれないと感じた。
実はぼくも昨年の6月、仕事場の屋根に太陽光発電パネルを設置した。屋根いっぱいに24枚のパネルを並べるとマックス4.44kwの発電が可能だ。また、居住地域の発電効率が全国的にもトップクラスだったことも設置の後押しをした。(ちなみに第一位は北海道)タイミング良くもっとも効率的な初夏から稼働開始したので、太陽の力はすぐに実感することができた。ストックできない発電された電力は、まず自分が使用する。そして使い切れない電気は自動的に電力会社に送電されるようセットされている。室内に設置された電力モニタパネルを見ていると、リアルタイムで消費電力と売電の数値が変動していくのを確認することができる。これまで漫然と電気を消費していたのに、電力の流れが視覚化されたとたん俄然意識に変化が現れてくるから不思議だ。極力無駄な電気は使わずに、LED照明などを増やしたりして余剰電力を売電に回そうと意識するようになる。契約時の売電価格は買電の倍近くで、電力受給の契約期間は10年間保証されている。(ちなみに太陽光発電を促進するこの制度への補填のために、一律請求には太陽光促進付加金があらかじめ組み込まれている)
売電意欲が高まるのは単純な損得感情によるものだが、これも一種の省エネ意識への誘引と言えなくもない。なぜなら買い取り料金率が変わらないことを前提に売電し続けても、設置標準価格が回収できるまでには10年から20年ほどかかる計算になる。パネルの寿命は20年以上といわれているが、電気を利用できるように変換するパワーコンデショナーユニットの寿命はほぼ10年で、現在30万以上するこの機材の交換費用などを加算すれば、費用対効果としては決して割の良いシステムとはいえないからだ。
しかし、少しでも辺りが明るくなれば、とたんにパネルはせっせと働き始めてくれる。もちろん曇り日や日没後は発電しないし、いまのところこれですべてが賄えるほどの発電能力もない。それでも日々頭上で発電していることを実感していると、やはりこれは自然に対して逆らっていない正直な科学なんだという気がしてくる。別にぼくはソーラーパネルをすぐにでも設置した方がいいとか、すべきだともまったく思っていない。やりたい人はやったらいいし、興味なければスルーすればいい。これからは急速に設置費用は安くなっていくだろうし、それを考えると設置するタイミングは悩ましい問題である。
先日、ナノテクノロジー (nanotechnology) の特集番組がTVで紹介されていた。それによると、画期的な太陽光発電システムが急ピッチで実用化に向けて開発されているらしい。パネルは太陽の可視光しかエネルギーに変換できず、半分以上を占めている赤外線はまったく再利用されていない。ところがこの新しいナノテクノロジー は、地球に届く太陽の大半のエネルギーを効率的に電力変換することができるのだという。まだ乗り越えるべき課題も残されているようだが、実用化されれば地球上すべての電力をまかなうことも不可能なことではないらしい。それに設置費用もパネルに較べたらはるかに安い(およそ20分の1)。また液状の集光物質も開発されていて、これなら例えばビルの壁面などに塗れば、それがパネル替わりになるので発電スペースは飛躍的に普及することになる。こうした夢のような技術は遙か彼方の夢物語などでなく、現に実現化に向けて急ピッチで進められているのだ。また、風力発電がヨーロッパでは普及しつつあるようだが、それより日本で大きな可能性を秘めている地熱発電が、これも安価で効率のよい技術の実用化に向けて実験段階に入っているという。 だからぼくは科学を進歩させていく人間の潜在能力に対してはけっこう楽観している。ほんの10年前にデジタル技術がこんな変貌をとげると誰が予想しただろう。現実界の変化に追いつけないのは実はぼくらの意識の方であって、昔はあんな大袈裟なパネルを何枚も屋根に乗せていたんだよね、なんて笑い話になるのもそう遠い日のことではないだろう。
3.11で原発はかなり危ない科学だったと骨身に沁みた日本人。右肩上がりの経済偏重幻想からそろそろ解き放たれて、これを機に進むべき道を考え直さなければならないと漠然と考えている人はたくさんいるだろう。機を見るに敏な作家、五木寛之氏の新作『下山の思想』が最近話題となっている。こんな現象にも今の日本を覆い尽くしている気分が象徴されているようだ。
東北の太平洋沿岸で原発が唯一作られなかった岩手県について、三陸の網元の家で生まれた元首相、鈴木善幸を抜きにその歴史は語れないというコラムが朝日新聞に掲載されていた。1975年頃から岩手三陸では原発誘致をめぐって世論が割れつつあった。しかし、地元選出の善幸はいっこうに態度をはっきりさせることなく、中央と地元では別な顔を見せながら決着を先延ばしし続けた。白黒つければ禍根を残し、後戻りできない対立を生む。善幸は「和の政治」を掲げ、足して二で割る典型的な政治家だったから、粗末な漁港をせっせと改良し続け時間稼ぎをした。そして結果的にこの共同体の亀裂を忌み嫌う手法によって計画は立ち消えになったという。小泉、橋本手法と対極にあるようなこの古風な「和の政治」は一見時代遅れにもみえる。しかし敗者を生み出すだけの二項対立政治では守り切れない大切なものがこの日本にはまだたくさん残されていることを考えたら、可能性を宿す手法として記憶しておいてもいいのではないだろうか。山頂はひとつでも、下山道はさまざま。選びとることの重要性を時代が求めはじめている。
ただ、科学の進歩に楽観的なぼくでも、人間のエゴや倫理に対しては悲観的にならざるをえない。退化こそすれ、決して進化などしていないのは古今東西、歴史的にも明らかだ。どこに向かって科学技術を進歩させていくのか。地域や国家や民族性やさまざまに錯綜した問題を整えながら、本当に日本人にとって必要とされる未来を包括する深い射程をもったビジョンが今切実に求められている。ところが、震災以降出てくるのは、経済問題に終始する短期的視点によるうんざりするような議論ばかりだ。これから進むべき方向性を人々は本能的に直感しているのに、そこに重なり合う強靱な新しい理念がこの国には決定的に欠乏していた。
しかし、光の兆しはある。それは大震災からおよそ3週間後の中沢新一さんの発言からはじまった。中沢さん、内田樹さん、平川克美さんの3人は2011年の4月5日、Ustreamで配信される番組「ラジオデイズ」で大震災と原発事故について語り合った。まだこの時点ではどう対処すべきか思いあぐね、はっきりと発言する知識人はほとんどいなかったにもかかわらず、そこで中沢さんは果敢に根本的な問題点を指摘しながら、ドイツの「緑の党」のようなものをつくるという構想をあきらかにした。(経緯はこの対談をまとめた2011年5月出版の『大津波と原発』(朝日新聞出版)に詳しい)
さらに息つく間もなく、『すばる』(6、7月号・集英社)で「日本の大転換(上・下)」を発表。(8月には集英社新書として発刊)ここで大津波と原発事故がもたらした災禍をきっかけとして、わたしたちがとるべき選択肢を明快に提言している。特に印象的なのは原子力技術の宗教思想における対応物が、実はユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった一神教であるという指摘だ。巨大な原子炉ともいえる太陽は生態圏外に存在するが、生態圏の中に人間はもうひとつの太陽をたくさん作り出してしまった。その生態圏に「外部」を持ち込もうとする思考方法が、互いに親和性を保ちながら、科学では原子力を、宗教では一神教を、経済ではグローバル型資本主義を発達させてきたのだという。だから今回の原発問題は単なる科学や経済といった単一の領域にとどまらず、実に巨大で根深い、まさに文明の根幹にふれている問題なのだと指摘している。つまり日本は大きな試練にさらされていると同時に、今後の世界が目指すべき新しい道を指し示すことができる可能性も同時に秘めていることになる。ぼくの拙い説明などでなく、ぜひ新書を手にとっていただきたい。そこには3.11以降の危機的事態を重層的に明らかにしながら、これからぼくらが進むべき行程が示されている。願わくばもう一冊手にとってほしい本がある。1月30日角川書店から発刊された、出来たてほやほやの内田樹さんと中沢さんの渾身の対談集『日本の文脈』だ。(企画編集はチーム・ミクロでご一緒した平林享子さん)この本は『日本の王道』というタイトルで出版されることになっていたが、3.11の大震災で日本を取り巻く世界の文脈がすっかり変わってしまい、もう前のようには「日本的なもの」の原理を心安らかに語っていることができなくなってしまった。だからこの激しい変化の渦中にある日本の文脈のなかに、自分の原理をみずからの力で戦い取らなければならない。そのために送り届けられようとしているのが『日本の文脈』であると「まえがき」で中沢さんが書いている。対話集とはいえ、広くて、深くて、力強い。そして読後、日本人は本来何処によって立つべきか、ストンと腑に落ちる。
「緑の党」のようなもの発言で何やら政党部分が拡大報道されている感があるが、実は中沢さんが構想しているのは「グリーンアクティブ」というゆるやかなネットワークを基軸とした活動で、政治班はその一部分にすぎない。詳細は2月に予定されている記者会見をもって発表されるそうなので、ここで明らかにすることはできないが、こうした大いなる「贈与」に向かって一心にエネルギーを注ぎこむ中沢さんの感動的な一連の試みに、ぼくはたしかな光の兆しを感じている。 『日本の大転換』の「リムランド文明の再生」という章には、周縁の国である日本列島などで形成されてきた文明の特質についてこのように語られている。
「外部との境界には、遮断力の強い壁ではなく、透過性にすぐれたさまざまなインターフェイスの仕組みが設けられた。インターフェイスは外部に属する諸力を内部に折り畳んで組み込む働きをもっていた。外部からの力を、壁で遮断するのではなく、幾重にも媒介をほどこしながら、内部に取り組んでいく仕組みである。 火山が多く、地震にも頻繁に見舞われてきた日本列島では、自然力を外に押し戻したり、ブロックしてしまうのではなく、インターフェイスの機構をつうじて、媒介的に自分の内側に取り込む方法が、さまざまな分野で発達した。(集英社新書『日本の大転換』94ページより抜粋)」
こうしたリムランドの特性があらゆる分野にまで浸透し、長きにわたり培われてきたのが、ぼくらの暮らしてきた日本という国の文明だった。しかしここ半世紀あまり、グローバル型の資本主義によってリムランド文明は土台からの破壊にさらされてきた。そのインターフェイス分断が続く危機的時代に、今ぼくらは生きている。
「新しい日本」が目指すべき進路は見えている。そこに向かって、可能性を現実に変える理念をたずさえ歩き出すしかない。その先にはたったひとつの太陽が眩しく輝いているはずだ。
