



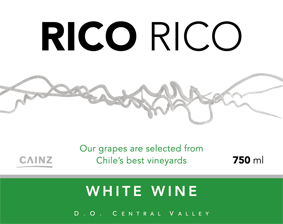
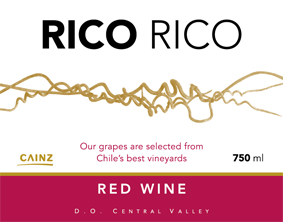








茶碗の葡萄酒
ぼくはまったくといってもよいほどアルコールが苦手なので、正真正銘の「下戸」と言えるだろう。対義語には「上戸」があてられていて「うわばみ」とか「ざる」とも呼ばれている。さしずめ横綱格は「酒豪」というところか。元来、「戸」とは律令制の課税単位のことで、婚礼のとき酒量を決める際に「上戸」「中戸」「下戸」と定めたことから、酒の飲めない人を「下戸」と呼んだのが由来となっているようだ。
まず、アルコールが体内に入ると肝臓には、紅潮、頭痛、吐き気、頻脈などを引き起こす毒性の強い「アセトアルデヒド」という物質が分泌される。これを分解するのが「アルデヒド脱水祖素酵素2=ALDH2」。「下戸」はこのALDH2の活性が低い「低活性型」もしくは「不活性型」と呼ばれる体質であるといわれている。実はALDH2はモンゴロイド系特有のもので、ヨーロッパ系やアフリカ系にはみられないんだとか。
そんなアルコールが苦手なぼくが、唯一少しだけ口にできるお酒がある。それはワイン。麦から作るウイスキーやビールは駄目なのに、葡萄から造るワインなら少しだけ飲めるということは、もしかしたら、なだらかな山辺に広がる葡萄棚に囲まれた風景の中で育ったことと無縁ではないのかもしれない。デラウェアや地元の固有種である甲州などの生食用葡萄を栽培する畑が、暮らした自宅周辺には数多くあった。小学校の通学路もそんな葡萄畑の脇道だったから、季節によって変化していく畑の様子も幼少期の懐かしい残像となっている。
ところで、あと1ヶ月で21世紀になろうかという時に、山梨県立文学館の開館十周年を記念してコンパクトな本が刊行された。あとがきには当時の館長であった紅野敏郎氏によるこんな記述が残されている。「…文学館開館十周年の記念品の話が出たとき、井伏の「甲州」にまつわる随筆を精選して編むことがベスト、ということに決まりました。「コルボオ叢書」の一冊になっている『厄除け詩集』のような、瀟洒で、身近に置いて読みやすい、滋味深い本、これを皆さまにおとどけするのが、文学館らしい風貌姿勢と判断いたしました。風貌姿勢という言葉は、井伏鱒二の愛用語です。「甲州」の自然と人ともかかわり、あたたかく、きびしいまなざし、抑制の利いた文体、それをこの本から読みとっていただければ幸甚です…」
こうして、甲州との体験を根っことしたふくよかな作品7編がおさめられた「井伏鱒二 甲州随筆選」が刊行され、ぼくはこの小冊の装幀を担当した。そこにとくに印象深い、好きな小編があって、その4頁にも満たない「葡萄の村」は本の最後におさめられている。1941年、『新女苑』11月号に発表された作品だが、最後の数行を転載する。
*
「…山のなかの工場とはいへ、今まさに活気旺溢のところである。同時に、山麓の農家でも各自の忙しさに違いはない。御主人は総指揮を相勤め、奥さんやお嬢さんまで自ら動員して青果を籠に詰めてゐる。雇ひの人は発送の荷造りをする傍ら、ほの暗い納屋に入って葡萄酒搾りも勤めるが、その機械といふのが甚だ原始的である。ハンドルを廻すとギイガラガラといふ音がする。
しかしこのやうな活気も忙しさも、秋が終わると共にすべておしまひになる。葡萄棚の葡萄はすつかり摘み尽くされ、葡萄の葉は海老色に色づいて来る。さうして、やがて初めてひと霜の来る夜は、一夜のうちに葡萄の葉がみんな散り尽くしてしまふ。葡萄の葉は一せいに散る。その散る音ははらはらと散るなどと、形容するやうな生ぬるいものではない。
広い広い幾つもの葡萄畑の葉が、みんな一夜のうちに散つてしまふ。ばらばらばらざあざあざあと音をたて、まるで木立のなかで時雨の音を聞いてゐる感じである。夜ふけにこの音をじつと聞いてゐると、誰しも疑ひなく万感胸に迫つてゐるものがある。幾ら葡萄園に住みなれたお婆さんでもお爺さんでも、この物淋しい音を聞く夜は、きつと夜眠ることができないだらう。ざあざあざあ……ばらばらばら……と散つてゐる。きつとお婆さんもお爺さんも、寝床から起きて来て炉の火をかきおこし、戸外の葡萄の葉の時雨の雨にじつと耳を傾けてゐることだらう。」
*
この時、時雨の音に耳を傾けているのはお婆さんやお爺さんだけではない。子どもだったぼくも、まだ薄暗い朝方の寝床の中でたしかに何度も聞いていたのだ。そうして、冬の気配を届ける葡萄時雨の季節が何度も通りすぎていった。枯れた葡萄の葉が晩秋の風にあおられ、擦れて出るおよそ植物らしからぬ独特のガラガラという乾いた響きは、「冬がもうそこまでやってきているぞ」という葡萄畑から届く合図だった。だからぼくにとって、グラスの底に沈殿するワインにまつわる記憶のルーツは、葡萄畑が奏でる時雨の音をいっぱいに浴びた酒樽から立ちのぼる香りの奥に漂っている。母親の生家は比較的大きな葡萄園を営んでいたので、ひと山越えて折々に遊びに行った時の思い出は葡萄にまつわるものがとても多い。収穫時期ともなれば甘酸っぱい香りが充満する作業場の片隅で、搾りたての果汁100%の葡萄ジュースをふんだんに飲むことができたし、みな大人たちは、一日の仕事が終われば自家醸造した一升瓶に詰めた葡萄酒を茶碗に注いで酌み交わしていた。だからワインを口に含むと、そのフルーティーな口当たりの奥から、漂ってくる香りとともに葡萄色の懐かしい記憶も蘇ってくる。
長じて、ぼくはデザイナーとなり、ワイナリーの醸造家らとのおつきあいや、ラベル・デザインなど、ワインとの係わりも次第に増えてきた。それに地元ではワインは重要な地場産業と位置づけられているので、風土や地域文化を引き継ぐ産業としての期待も背負っていて、食生活の変遷に伴ってワインに対する認識も変化してきたので、もうワインを葡萄酒なんて呼ぶ人は今ではほとんど見かけることもない。
ワインはフランス語で「Vin」、英語で「Wine」、イタリア語では「Vino」、ドイツ語は「Wein」と、ヨーロッパ発祥の果実酒というイメージが強いが、きわめて歴史の古いこの酒は新石器時代にすでに醸造されていたとされている。世界最古のワイン醸造の痕跡はジョージアで発掘された紀元前8000年前の陶器の壺の発見によって、この地が現時点では最古の発祥地。ジョージアはコーカサス山脈の南麓、黒海の東岸にあたり、北側にロシア、南側にトルコ、アルメニア、アゼルバイジャンと隣接する交通の要衝で、日本では2015年までグルジアと言われていた国だ。そしてワインは中東、イラン高原、古代エジプトなどを中心とする広い地域で愛飲されるようになり、地中海岸沿いを拠点としていたフェニキア人によって古代ギリシアやローマ帝国を経て、広くヨーロッパへと伝播されていった。キリストがワインを自分の血と称したことからワインはキリスト教の聖餐式において重要な道具となったのは有名な話だが、この中世ヨーロッパでは儀礼のための飲み物であったから、日常の飲み物として広まるようになったのは中世後期からと言われている。そして、ブルゴーニュワインが銘酒として有名になり、ルネサンス以降、娯楽としてのワインの飲酒として発展、定着して現在に至っている古典的な果実酒なので、ワイン醸造家や愛好家らは深いこだわりをもってワインと向き合っている。ワイナリーの経営者はどことなく他の地場産業者からは感じられない独特の誇りをもってワイン造りをしている印象が強い。様々な物語を内包するワイン造りの風土は、一つの文化であるという誇りなのだろう。ワインを愛飲する人々からも、その奥深さを愛でる楽しみとこだわりがミックスされた、これもある種の誇りと呼べるような意識が感じられる。
だからぼくは、そうした世界観によって成り立つワインとデザインを通じてかかわる場合には心して向き合わなければと考えてきた。ワインの産地で昔から活動してきたので、必然的に多くのワインのラベルデザインをしてきたが、とくに記憶に残っているのが、CAINZの『RICO RICO』Wineだ。サントリーが輸入元となったチリワインの白、赤、ロゼのシリーズで、初期デザインと第二期デザインの2タイプがある。「RICO RICO」とはスペイン語で「美味しい!美味しい!」という意味らしいが、「安くて、しかも美味しい」をアピールしたこの商品は、売場ではダンボールに納まって山積みされるので、とにかくスッキリとシンプルで分かり安いイメージとなることを意識してデザインした。初期デザインは白と赤の2アイテムでスタートしたので、落ち着いたグリーンとワインレッドの配色にアクセントカラーのシルバーとゴールドを振り分けた。そしてメイン・ビジュアルには螺旋状に絡み合う葡萄の蔓を金銀で刷り分けた
元来、葡萄は蔓植物で、植物学ではヴィティス属 / ブドウ属と分類されている。蔓性の植物は蔓の先端を不規則に動かしながら伸びて支柱などに触れると、接触した反対側の細胞が伸長し、その結果蔓が支柱に巻きつく葡萄は「巻きひげ類」のタイプに属する。(『三省堂新生物小事典』)子ども時代に枯れた葡萄畑の脇に刈り取られ積み上げられた葡萄の蔓を散々みてきたから、使い古された葡萄の房なんかでなく、ぼくはこの独特な形状の蔓にフォーカスしてみようと思い定めていた。丁度季節も秋になっていたので、さっそく傾斜地に葡萄の畑が広がる近くの山の麓に向かい、何本か枯れた蔓を採集してきた。あらためて観察すると実に有機的で複雑な形状をしている。電子顕微鏡で覗いたことはないけれどDNAの二重螺旋構造を連想させるオーガニックでエレガントなフォルム。これという蔓を選び出し、接写して切り抜き加工を施して白地に横に配置すれば、ワインボトルを並べたときにボトルを束ねるロープのようにも見えるはず。幸いデザインも好評で異例のロング&ベストセラーとなった
そして数年が経ち、初期ラベルのリニューアル依頼が入ってきた。さて今度はどうしようか、としばらく悩んだすえにイメージを一転させ、有機的な形状で可愛らしい、子どもの絵本のようなラベルにしようと考えた。モチーフとしたのは17〜19世紀にイングランド、フランス、イタリアで制作された刺繍のためのスケッチを元にした。刺繍するための下絵なので、見られることを意識していないから、線も自由闊達でのびのびとしている。×印はボタンの付く場所というのもご愛嬌。(このイラストは「ミクロコスモスⅠ・Ⅱ」の書籍デザインでも活躍してくれた)モノクロの線画に塗り絵の要領で着彩を施すとカラフルでファンシーなイメージに生まれ変わって、思いのほか可愛らしいワインラベルとなったと思う。
変化していくということはどういうことなのか。愛着のあったものを捨て去り、明日の後ろ姿に目を凝らす決意表明なのだろうか。愛着と飽きは常に表裏一体で存在するもの。もうそろそろ変わらなきゃって腰を上げる変化もあるし、稲妻に打たれたような衝撃が促す変化もある。このワインラベルシリーズの変化は性格の異なる姉妹と向き合うような戸惑いもあるのだが、ぼくはどちらにも忘れがたい愛着を感じている。
ワインは発祥地域の文化風土を纏って、豊潤な広がりと深淵な風味を楽しむ、とても奥深い世界を届けてくれる飲物だ。もちろん他のお酒だってワインと遜色のない独自の魅力を湛えているのだが、ワインにはどことなくスタイリッシュでお洒落なイメージが根付いている。ワインと言えば、ぼくは仕事の資料として、2000年前後に美術出版社から季刊で発行されていたワイン専門誌『Winart(ワイナート)』を定期購読していた。特にワインに興味があったということでなく、購読理由は別にあった。本誌のArt Directionを担当していた岡本一宣氏の仕事を見たかったからだった。この『ワイナート』以外に新潮社の『SINRA(シンラ)』や文藝春秋の『ノーサイド』といった雑誌で、岡本一宣氏のデザインにはずっと興味を抱いていた。一言で言えば彼のデザインは、歌舞伎の見得に近い気がする。(歌舞伎で「見得(みえ)を切る」というのは正しい言い方ではなく、本来は「見得をする」が正しいのだそうだ)モダンでシンプルで歯切れがよく、イメージ写真に大胆にメリハリをつけた文字を配置して、(極端に大小を付けて対比させる手法)当時、イッセン風と呼ばれるスタイルを確立していた。メインはずっしりとした和文のモリサワゴシックMB101シリーズ。そして、繊細なセリフ書体の英文字を小さく添えてアクセントとする。こうして文字に密度の差をつけて対比させるテクニックと、そこに色文字を組み込んで、文字をビジュアル化していく特徴的なバランス感覚は音楽的ですらあった。一見やり過ぎ!と思えるのに、全体感ではやはりちゃんとバランスをとっている。料理の盛りつけをさせたら間違いなく素晴らしい仕事をするに違いないと思わせるような、ぼくとほぼ同年輩の長崎出身のエディトリアル・デザイナーだ。念頭に置いている言葉は「美は存在の力」だという。その言葉は、自身の美意識に寄せる信頼の大きさを物語っている。厚みが7cmもある、ぶ厚い彼の作品集の表紙タイトルは『岡本一宣の東京デザイン』と命名されている。ここに「東京デザイン」とあるのは何故なんだろう。面識はないので確かめようもないのだが、距離感や密度の違いでなく、長崎から東京までの心の大地の道程が、どこかワインを通じて希求する道程と重っているのかもしれない、と思ったりもした。ワインの本家とされるヨーロッパへの憧れと、ここにしかないもう一つの日本独自のワインの世界を育てあげることへの情熱。その二つがブレンドされた道程の先にある「存在の力」と言い切れる、なにものかを求める旅。
と、ここまで考え、酒の飲めないぼくは、子どもの頃に見た光景へと再びループする。どうしても、大人たちが手にした茶碗に注がれたあの葡萄酒のことを思い浮かべてしまうのだ。子どものぼくには口をつけることのできなかった、あの茶碗酒。ぼくにとってのワインは、深淵な風味の世界を湛えるWineでなく、やっぱり、時雨音の染み込んだ葡萄酒だ。未だ飲んだことのない、未来が注がれた葡萄酒なのだ。どこか遠くから、高田渡の歌声 『酒が飲みたい夜は』が聞こえてくる。
