
最新ポップミュージック
ぼくはDJの草分け小林克也さんが大好きだ。克也さんが1975年に桑原茂一とプロジェクトを開始して、その翌年に伊武雅刀を加えたスネークマンショーには、ラジカルなコントに挿入される先鋭的な選曲センスを存分に楽しませてもらった。その克也さんも1941年生まれで今年76歳。2006年に胃がん、2012年には前立腺がんを患ったものの見事に復活し、今年「小林克也&ザ・ナンバーワン・バンド」名義で25年ぶりのオリジナルアルバムを発表するなどと気を吐く永遠のロック小僧ぶりは健在だ。その彼のライフワークともいえる洋楽番組「ベストヒットUSA」は1981年にスタートしている。中断もあったが2003年からはBS朝日で復活。欠かさず見るというほどでないが、ぼくはチャンネルサーフィンで放映中だとつい見入ってしまう。ロックの創成期からずっとリスナーとして並走してきたからこそ見えるポップスの神髄をシンプルなコメントで伝えてくれる克也さんは伝道師として、今とても貴重な存在だ。
しかしベストセラー書籍と同じで、万人受けするポップミュージックはめったに琴線に触れることがなかったので、ぼくはずっと和洋ポップスから遠ざかっていて、一癖も二癖もある音楽ばかり好んで聴いていた。海外のポップスを耳にする機会は少ないが、国内のヒット曲などは日頃テレビから流れてくるのでそれなりに触れてはいた。しかし、どれを聴いても同じテンポの一卵性双生児のような曲ばかりで見分けはつかないし、もちろん琴線に触れることもない。それでも英語のフレーズをサンドした早口歌詞に耳を澄ますと、思いのほか生真面目な内容だったりするので楽曲とのギャップに軽く驚いたりもするのだが、「ベストヒットUSA」を見ているそんなぼくに克也さんは「いやいや、中にはイカしたやつもあるんだぜ。こんなのはどうかな?」とヒット曲を毎週見繕って聴かせてくれる。
昔はラジオにかじりついて音楽番組に夢中になっていたが、今はミュージックビデオ。つまり楽曲をアピールするために制作された曲とイメージが統合されたいわば短編映画と一体で味わうのが一般的な音楽の楽しみ方となっている。業界的に表現すれば、音楽録音の販売促進を目的としたマーケティングデバイスということになるのだろう。それにともなって聴き方もラジオから流れる曲を受信して想像力を駆使しながら自己編集していた聴き方から、一方的に発信されるイメージを受け止める味わい方に変化している。ミュージックビデオの発祥はザ・ビートルズにまで遡るという説が一般的に浸透しているようだ。新曲がリリースされるたびにテレビ番組に呼ばれることにウンザリしていたビートルズは、演奏シーンとイメージ映像をドッキングさせた映像作品を発明した。それがミュージックビデオの起源であるという説だ。こうした現象は1980年代にアメリカに登場したMTVで急速に一般化していった。 (MTVとはMusic Televisionの略でニューヨークとロンドンに本部を置くアメリカの若者向けのケーブルテレビ・チャンネル)
はじめの頃はライブパフォーマンスを撮影したビデオが主流だったが、次第にアニメーションを含む幅広い撮影技術を駆使したさまざまなアプローチが試みられるようになってきた。そしてミュージックビデオは1983年にリリースされたマイケル・ジャクソンの「スリラー」で一気に市民権を得ることになる。「スリラー」は、いうまでもなく有名なおよそ14分にもおよぶホラー映画風のショートフィルム。特殊メイクの狼男やゾンビが繰り広げる演技やダンスが楽曲と渾然一体となった作品は当時のミュージック界に衝撃を与えた。ちなみにこの作品はショートフィルム史上初のアメリカ議会図書館永久保存フィルムとなっているのだそうだ。当初は映画監督が手掛けることが多かったが、やがてミュージック・ビデオ専門の監督が誕生する。逆にそこから映画監督に転身した人物も多いという現象まで生まれていて、ポップミュージックは聴覚と視覚を一体化した表現として日々世界中で生み出されている。
昨年末だったか、いつものようにぼくが「ベストヒットUSA」を観ていたら、2017年の総括番組としてビルボード (Billboard) シングル年間ヒットチャートが紹介されていた。アメリカで最も有名な音楽チャートであるBillboard Hot 100からベスト20曲が流れてきて、「なるほど、これが今の洋楽シーンのサウンドなのか」と聴いていたら何だか興味がわいてきた。実はこれには伏線があって、ぼくはカナダのポップミュージシャン、ジャスティン・ビーバー(Justin Drew Bieber)のアルバムや曲を何十曲もダウンロードして愛聴していたのだ。これもきっかけは「ベストヒットUSA」である日流れていた「What Do You Mean?」。ビーバーは才気溢れる青年だが、驚いたのは彼の世界観を腕利きプロデューサーや名うてのプロたちが綿密なチームワークによって協働作業しながら実現していたことだ。新世紀のポップミュージックは個人からチームにバトンタッチされたかのようで、それからというものぼくはビーバーの曲を集めては楽しんでいた。イマだなぁと感じたのは、徹底してデジタル編集されたクリアでシャープなサウンド。80年代ロックが地上波時代のモゴモゴとしたサウンドとすれば、ビーバーサウンドは4Kや8Kといったエッジの効いた高解像度音。そして音源の位置まで感じさせる、いわばハイレゾ的な広がりと余韻までも再現されている。さらに表現力を支えるテクニックも格段に進化している。彼に限らず世界的な現象としてテクニックはすごく底上げされていてみんな当たり前に上手なので、懐メロがやけに素人くさく感じられてしまう。もちろん昭和の味わいも否定はしないが、やはり時代は確かに流れているんだと実感する。もちろん、音楽を成立させる原形は魂のバイブレーションであることに変わりないし、技術やテクニックが魂にバイブレーションを起こすわけでもない。ただ、受信機の基準値が変化しているのは事実なので、それを念頭に表現と向き合わなくてはならない。これはなにも音楽に限ったことでなく、多くのジャンルの共通現象でもあるんだと思う。
そこでぼくはYouTubeで2017年のBillboard Hot 100を全曲チェックして、そこから30曲ほど気に入った曲を選び、暇さえあればiTunes Storeで楽曲購入しては、就寝前や車中や散歩中のBGMなど様々なシーンでじっくりと聴いている。すると少しずつ気づくことも出てきたのだが、例えばイントロが一様に短い。この謎はすぐ解けた。楽曲はiTunes Storeなどからネットで1曲買いするのが主流となってきているので、購入するかどうかは30秒ほど可能な試聴で判断される。つまり、昔のような長〜いイントロはすぐスルーされてしまうのだ。必然的に、瞬時に心を掴む楽曲組み立ての工夫が求められてくるわけだ。ちょっと世知辛い傾向ではあるが、これも時代の要請なのだろう。また、音が隅々までデジタル化されているから、音像がくっきりと粒だって感じられるので刺激的。触覚的ですらある。ぼくが夢中になって聴いていた頃の音楽、たとえばロックバンドの典型的編成といえば、ボーカルの両サイドにリードギターとリズムギターが控え、バックでベースとドラムスが支える編成。そこに時にはキーボードなどが脇から情感を醸し出す。こんな感じだったが、現代の楽曲構造はほぼデジタル音で組み上げられていて、ボーカルでさえ一つの楽器と位置付けられている印象がある。歌い演奏するミュージシャンが主役だった時代から、制作環境も大きく変わった今、その座は楽曲を組み立てるプロデューサーにバトンタッチされたかのようだ。必然的に音楽を創る人々の意識やそれに伴うスタンスも微妙に変化してくる。たとえば音楽と向き合う自身を冷静に俯瞰する視点、そして楽曲がどのように時代と関係性を結んでいくのか戦略的に構想する視点などが求められている新世紀のポップミュージックは実にクールだ。もちろんこれはぼくの私感に過ぎないのだが…。
その良い例が「PPAP」。2016年にYouTubeに投稿された「PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) =ペンパイナッポーアッポーペン」で一躍注目を浴びたピコ太郎こと古坂大魔王(本名・古坂和仁)は所謂ポッと出芸人ではなく、お笑いタレントやDJと並行して、テクノを取り入れた音楽コントなどを模索してきたミュージシャンの経歴を持つ人物だった。彼がテレビで「PPAP」誕生にまつわる話をしていて、これはなかなか興味深かった。わずか45秒の「PPAP」はギネス世界記録「全米ビルボードトップ100に入った世界最短曲」として認定されたとして話題になったが、この45秒間に古坂のさまざまな試行錯誤の成果が詰め込まれていたことがこの番組で明らかにされていた。例えばリズムを彼は100パターン以上用意して、どのスピードが楽曲コンセプトにもっとも相応しいか検討したそうだ。早すぎても意味が定着する前に流されてしまうし、逆に遅すぎると間延びして独特のユーモアが伝わらないと、間合いや強弱にも計算を尽くしている。また、制作予算がわずか10万ということもあって最小限のシンプルな設定にしたことが功を奏し、その真っ白いバックが子どもでも簡単に真似出来るダンスを際立たせているし、エンディングのヘロヘロ音も「偉そうな荘厳なサウンド」から「未知との遭遇風のサウンド」やら幾つものバリエーションから選び出されている。新旧の電子楽器を駆使して綿密に組み立てた戦略的かつ計算し尽くした制作方法は、現代の音楽界を席巻しているポップミュージックの制作方法に極めて近い。古坂はジャスティン・ビーバーを頭の隅にどこか意識しながら作ったと告白していたが、結果は彼の目論み通りとなった。「PPAP」が世界的に一気に拡散されることになったのは、この動画を見たジャスティン・ビーバーがツイッター上に紹介した「インターネット上の私のお気に入り動画」だったことは有名な話となっている。古坂大魔王は青森県青森市出身の44歳。2015年から青森市観光大使を務めている。かたや、その古坂がプロデュースするシンガーソングライターのピコ太郎は千葉県出身の54歳。78歳の新婚妻がいるとディティールもかなりきめ細かい。同一人物、一人二役なのにあくまでも二人は別人格という設定となっている。こうした物語を遠景として戦略的結晶の45秒の楽曲が据えられている。
ところで、Billboard Hot 100にランキングされている曲にラップ系の音楽が多かったのは意外だった。アメリカの若者がこれほどラップ好きだったとは!ラップはどちらかと言うとぼくの苦手なジャンルなので、魚の骨を選り分けるように避けてピックアップしたサウンドは、ロック・ブルース・ソウル・ラテン・カントリー・レゲエ・トランス・アフロ・アラブ・エレクトロニカ・ケルティック・サルサ・テクノ・ファンク・ヒップポップ・フォーク・ヘビメタ・マンボ・R&B・アンビエント等々、あらゆるジャンルの多様な地域性がフレキシブルにブレンドされていて、ここにあるのは分断された現実とはまるで別世界。人々の無意識に潜む願望が選びとった希求がポップミュージックの間から透けて見える。食わず嫌いだった最近のポップも向き合ってみると、なかなかどうして面白い。音楽に身をゆだねる快感に新旧はないのだから、もちろん昔の懐かしさも捨てがたいが、たまには新しい風に吹かれてみるのも気持ちいい。
※紹介写真ミュージシャンの各楽曲試聴は↓こちらから。
Rita Ora – Anywhere (Official Video)
Kyla La Grange – Cut Your Teeth
Anne-Marie – Ciao Adios [Official Video]
Calum Scott – You Are The Reason (Official)
Ed Sheeran – Perfect (Official Music Video)
Justin Bieber-What Do You Mean?
PIKOTARO(ピコ太郎- PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen Official)ペンパイナッポーアッポーペン
PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) (Long Version) [Official Video]
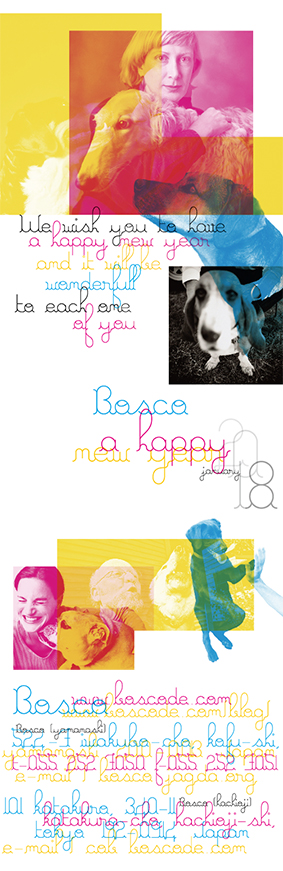
デザインを回想する
ぼくがデザインを始めたのは1974年。しかし実は71年から洋服店のショウウインドウ・ディスプレイなどデザインの真似事らしきことをしていた3年間があった。甲府駅前のビルの階段下にある極小空間を借り受け、リフォームを親戚の大工さんに頼んで赤・青・黄三原色の怪しげなオフィスを立ち上げた。そこでデザインオフィス(のようなもの)と手作りアンティークショップ(のようなもの)を並行させながら、まったく地に足はついてなかったが、今思い返せばかなり慌ただしい日々を送っていた。オフィスにはいろんな人が出入りを繰り返し、その頃がぼくの人生でもっとも喧噪に満ちた時期だったと思う。ただ2人分の机も並べられないほど狭い2坪ほどの空間では、次第にデザイン作業もままならなくなってきたので、ひとまず実家に戻り、応接間を占領して仕事場としたのが74年のことだった。事務所の電話番号下4桁を年号と同じ1974としたから創業年はよく覚えている。(ちなみに局番は51だから51-1974。「こい いくなよ で、仕事よ来い!出て行くなよ!」という語呂合わせ!)移転を考えていたときは、せっかく起業するのだからもっと見栄えのよい、どこか別の広い事務所を借りようかとも考えていたが、のちにメインクライアントとなる地元では知らない人はいないと言われるほど大成長した企業の社長が「無名の者に世間の人は1円だって恵んではくれない。余計な経費はかけないでもっと力がつくまでは自宅で充分」とアドバイスされ、実家の間借り起業を選択したのが20代半ばにさしかかる頃だった。
不遜もはなはだしいと叱られるかもしれないが、ぼくはどうしてもなりたいとデザイナーを目指したわけではないし、デザイナーという職業に憧れたこともなかった。そればかりか、やってることはデザイン以外の何ものでないのに、いまだに「気がついたらデザインをやっていた」とか「一応、デザイナーをしています」なんて言っている。
思い返せば、当時のぼくは間違いなくニート予備軍で、学歴はないし、教職免許も持っていない。それに会社勤めで人間関係を上手く築くなんてことはとても無理だと思っていた。実家に身を寄せるスネかじりの身のぼくに、実はデザイン以外にできることなど何もなかったのだ。そんな状況にもかかわらず、高校を出てからの2年間かなり濃密な美術修練の期間を経ていたので、ぼくは将来にさほど不安を抱くこともなく、根拠のない自信にあふれた生意気な若者だった。そして、「どんな人生になるのか分からないけど、好きなことをして暮らしたい」という人間として至極まっとうな、しかしとても困難を伴うに違いない漠然とした願いを抱いていたのだが、それは今ほど過酷な社会状況でなかった当時だからこそ許された楽天的希望だったと言えるだろう。ともあれ、ぼくのデザインの第一歩はこうして踏み出された。
ぼくが生業としたデザインはグラフィックデザインという分野で、主に印刷物を対象とするものだった。起業してから約20年後のパーソナルコンピューターの登場によって制作環境が一気にデジタル化されていくのだが、それまでのアナログ時代も印刷物が完成するまでの基本的制作プロセスはさほど変わらない。覚えなくてはならないことは山ほどあった。前述したようにぼくはデザインの専門教育を受けてないので、まったくの自己流で習得していくしかなかった。必然的に仕事が授業となり、現場が学校、各工程の職人さんらがぼくの教師となった。
当時はまだ写植という職種があって、ぼくらデザイナーは文字組を担ってくれる写植屋さんに依頼して印画紙に指定した文字を現像プリントしてもらい、それを版下という台紙に貼り付けてデザインを組み上げていく。写真はアタリと呼ばれるスケッチで指定しておく。こうして完成した版下の上に半透明のトレーシングペーパーを被せて色指定という作業に移行する。これはその名の通り色を指定していく作業。単色なら調色してインクを練り込んで作る特色という色選びをする。カラーの場合はCMYKという4原色を網点で掛け合わせて再現するので、仕上がりを想定して各色を%で指定していく。版下はモノクロだが、指定しているデザイナーの頭の中では視覚的にシミュレーションされたカラーが再現されているわけだから、今考えると相当高度なことをしていたことになる。それから次の工程で版下は製版屋さんに渡されて、そこで指定された情報に基づいてカラーごとに分色されたフィルムを作り、それをインクをのせる版に焼き付ける刷版という行程に移っていく。印刷屋さんこれら焼き付けられた版を印刷機に巻いて本刷りをする。最後に、刷り上がった印刷物は製本屋さんに渡されて、折ったり綴じたりの製本加工を経て印刷物は幾多の行程を経て完成する。このようにアナログ時代の印刷プロセスは、デザイナー、写植屋、製版屋、印刷屋、製本屋などが分業しながら一連の流れ作業で成り立っていた。したがって流れの源流に位置するデザイナーも1ユニットとしてそれなりの知識が必要とされていたから、ぼくは現場で場数を踏みながらそれらを習得していった。
ところが、90年代半ばに始まったデジタル化でこのプロセスが一気に統合されていくことになる。コンピュータで卓上出版するという意味のDTP(Desktop publishing)の到来は印刷業界に大きな変化をもたらすことになった。デザイナーは烏口を研いだりロットリングで細い線を引いて版下製作したり、ポスターカラーで彩色する必要もなくなった。また、写真植字はデジタルフォントに置き換わり、写植のプロセスも不要となった。さらに製版の一部はデザイナーがパソコンのアプリケーション上で分色指示することで統合され、また製版もフィルムが不要となって直接刷版するダイレクト刷版システムにより、一部が印刷に統合される現象も起きていった。計算上は、プロセスがシンプルになることによって制作時間と費用が縮小されることになるが、実質的には、デザイナーと印刷所の倍増した作業量は従来の料金に吸収され、写植と製版は消えていく業種となってしまった。また、デジタル変革はデザインのフォーマット化も生みだし、そこそこのデザインならわざわざ専門職に依頼しなくても、それなりの印刷物を仕上げることが可能となった。こうして世紀をまたぎ、大きく変わった印刷を取り巻く環境の中で、デザイナーは生き延びていく術を新たに模索しなければならなくなってきた。
ぼくは割合早い時期から製造メーカーのクライアントとの出会いがあったので、印刷物と並行してさまざまなパッケージのデザインもしていた。パッケージデザイナーはペーパーの印刷物ほど受注機会がないので地方都市では数えるほどしかいなかったと思う。パッケージは紙以外に各種フィルムや缶などの金属など広範囲な素材で再現するため、デザイン手法や工程、そして制約条件も複雑になり、覚えなくてはならないことが山積みされてくる。加えてデザイン業務はCIブームもあって、具体的な成果物を伴わない企業のシンボルマークやLogotype、略称CIのコーポレート・アイデンティティ(Corporate Identity)やCIを構成する要素で企業が伝えたいイメージを効果的に表現する作業の略称VIのビジュアル・アイデンティティ(Visual Idntity)とデザイン範囲はますます広がっていったので、アンテナはより高く、また広範囲に張り巡らさねばならない状況になってきた。
起業する25年ほど前にぼくが描いた計画図は、まず5年くらいは技術習得の期間に充て、主に印刷会社からデザイン作業を下請け受注して研鑽を積むというものだった。次の5年は収入の柱を一定額確保しながら、少しづつクライアントを開拓して印刷会社からの受注比率を抑えて、逆に発注比率を高めていく。目標通り、起業から10年ほどで受注と発注の割合は半々となり、やがて業務がほぼ発注で占められるようになるまで約15年ほど費やした。もちろんそのためには直接デザインを受注しなくてはならない。広告代理店を経由した受注もあったが、直接でないぶん情報が歪んでしまい随分回り道を余儀なくされたり、辛い思いもさせられたので極力直接クライアントから受注することを心がけてきた。相手の顔が見えるから言い訳が許されず、結果を問われるシビアな仕事になるけれどその分やり甲斐もある。ぼくの性分にはこの方が合っていた。
もちろん、山もあれば谷もあった。やせ我慢していた時期に「好きなことをして暮らしたい」という希望が度々くじけそうになったこともあったが、それでも何とかしのぐことが出来たのは、「自分にはこれしか出来ない」と「嫌なことはしたくない(=嫌な人とは付き合いたくない)」という退路を断ったシンプルな覚悟だった。来月はどうなってしまうんだろうと頭を抱えるときには、「くよくよしても仕方ない。ケセラセラ、なるようになるさ」と朗らかな歌声が心の中から響いてくる。すると、なにか大きな存在が天上で計らっているように決まって空いた穴を埋める出会いがあった。
長年デザインをしてきて、ひとつだけ分かったことがある。希望が実現される。それは人との出会いに尽きるということだ。幹から枝が伸び、葉を広げるときには必ず節目となる新しい出会いがあり、そこから新たなネットワークが構築されていく。それを用意するのは運なのだろうが、運を呼び寄せるのはやはり自分自身。楽になると分かっていても、あえて我慢して嫌な人とは付き合わないぞと思い定めると、不思議なことに好い人たちに囲まれるようになってくる。何をもって好い人というのかは人それぞれだろうが、ぼくの場合はまずウマが合うこと、そして仕事相手は狡くなく潔い人であることに尽きる。「朱に交われば赤くなる」と「類は友を呼ぶ」は手を携えて、枝は節目を重ねながら空に向かって延びていく。こうして歳を重ねるごとに起業時に描いた計画図に近づくことができたのは幸せなことだったとつくづく思う。
デザインは一人で完結するものではない。依頼があって初めてスタートラインにつくことができる。そこが芸術などの表現行為ともっとも異なるところ。だから、依頼が持ち込まれるまでは頭の中を白紙にしておかなくてはならない。いつ何時どのような依頼が舞い込んできても、頭の中の真っ新な紙にスケッチが始められるよう、自然体をキープしておかなくてはならない。もちろん信念はデザイナーを支える大事な要素だが、それは自己主張したり自己表現するということでは決してない。むしろ可能な限り自我は消して臨みたい。ある要望を持って依頼してくるクライアントと、その要望を伝えたい対象者が居る。デザイナーはこの両者のどちらにも偏ることなく、厳密な意味の中間点で依頼された要望の具現化に知恵を巡らす。往々にしてクライアントの要望は絞られておらず、混沌と散らかって収拾がつかない状態で持ち込まれることが多い。こんな感じのものが欲しいと具体的な要望を示されることもあるが、話を聞き込むと本来の要望点はその奥に潜んでいて、それではまったく解決できないケースも少なくない。依頼者の要望をできる限り叶えて提案することは当たり前だが、それだけで関係が持続するわけではない。ときには良い意味での掟破りも必要になってくる。小さなサプライズを提案に仕込んでおくことで関係の鮮度が保たれる。こんなこともさまざまな経験から学んできたことだ。
デザインはとても感覚的な仕事だと多くの人はイメージしているようだが、実は感覚が求められるのは全体の10%にも満たないのではないだろうか。大半の作業は散らかった課題点の整理整頓に費やされる。さらに市場調査やマーケティング情報も参考にしながら、関連資料の収集や仕込みが欠かせないとても地味な作業の積み重ねによって成り立っている。ぼくは大切なことは「直感」と「緻密な作業」のバランスなのだと思っている。例えば、ヒアリング段階でぼんやりとデザインの着地点が見えてくることがある。これしかないのではないかというくらい明快な着地点が見えてくることもある。こうした直感は往々にして鮮度も高く、外れることはあまりない。直感は日々蓄積される膨大な意識下の記憶量によってもたらされるものだと思うのだが、実はここからが本当は大事。着地点を具現化するための緻密な作業が求められてくるからだ。安易にゴールを急ぐとスカスカな着地点となってしまう。そこに至るまでの法則はないから、こればかりは各々のやり方で編み出していくしかない。
デザインは社会性を伴った視覚伝達行為であり、対象者の意識を喚起させる力を内在させておくことが求められる。多くの場合対象者は幅広い生活者となるため、時代意識として投影されるさまざまな暮らしの事象には広く(そして出来れば深く)アンテナをはっておかなければならない。例えばパッケージデザイナーにとって、スーパーマーケットが図書館となるように、普通の生活感に目をこらす。普通というキーワードは最大公約数の別称だが、時にはその普通を潔く切り捨てる勇気も持たなくてはならない。いかようにもシフトできる自在さを体得しながら、デザイナーは変化し続ける市場動向の奥にうごめく時代感覚に目をこらし、大胆に着地点を直感する事が求められる。それはいわば発信者と受信者との間に交信現象をもたらす現代のシャーマン(祈祷師)のような存在なのかもしれない。それが「好きなことをして暮らしたい」と漠然と願った若者がそれなりの紆余曲折を経て辿り着いた心境だ。そして、現代のシャーマンを目指し、真っさらな白い紙とできる限り長く向き合っていたいと新たな年のはじまりに、また漠然とそんなことを願っている自分がいる。

神社巡りがやめられない
昔から特別帰巣本能が強いのか、ぼくは家から遠く離れるほどに落ち着かなくなり、次第に引き籠もりがちな性分が形成されてきたようだ。仕方なく出かけた旅先では、枕の違いが気になって寝付けなかったり、すぐに体調が狂ってしまい一刻も早く家に帰りたくなってしまう。だから仕事がらみの遠出では余程のことでないかぎり、極力日帰りするようにしてきた。こんな放浪癖と対極にあるような性分なので、海外旅行などはぼくにとっては限りなくハード ルの高いものとなる。本来、旅行は退屈極まりない日常から抜け出せる楽しみとなるはずなのに、そうならないのはつくづく損な性分と言われそうだが、ぼくはこれっぽっちも損などとは思わずに、自分を限定づけるこんな性格と折り合いをつけながらこれまで生きてきた。
それが50歳も過ぎる頃から男の更年期症状というのだろうか、体調の変化が徐々に現れ、思い返せば還暦を迎えるまでの10年間はとても不安定な時期だった。病名がつくほど決定的に不調なわけではないが、まるでモグラたたきのようにいつも身体は不調の移動を繰り返していた。運勢によれば、60を越せば次第に安定期に移行していくとある。たしかに還暦過ぎるとそこが竹のひと節だったかのようにそれまでの自分から脱皮して、新たな自分に生まれ変わったような気がしてきた。時を同じくしてその頃から仕事の都合で定期的な出張に出ることになり、ほとんど日帰りなのだが群馬、埼玉、この両県に向かう機会が増えてきた。ただこの地域、電車だと乗り換えを含むとかなり時間がかかってしまう。そこで往復でおよそ300km強の距離を自動車で移動することにした。中央道から圏央道、そして関越道に乗り継ぐルートをここ数年で通算300回近く往復してきたのではないだろうか。車は基本的に自分のペースで移動できるので、わがままなぼくには向いている移動手段と言えるし、元々運転が嫌いではないのでさほど疲れも残らない。それやこれやが契機となったのか、その後ぼくの帰巣本能にも少しずつ変化が現れ、小旅行ならさほど苦にならなくなってきた。現金なもので、人生の折り返しをとうに過ぎたのだから、これまで自身が封印してきた旅行をここらで少しづつ解いてみようという意欲が湧いてきた。
そこでぼくは毎月2~3泊の小旅行をすることにした。もちろん仕事の都合もあるからそう長くは休めない。本当なら一週間から10日ほどの休暇をとって遠出もしたいところだが、そうもいかない。ならばせめて毎月は出ることにしようと、ここ数年は判で押したように毎月出かけ、その旅先は相当な数になるが、指を舌で湿らせて風の吹くまま気の向くまま、寅さんのような気軽な一人旅を心掛けている。旅先は車で移動可能なエリアなので、暑い時期は比較的涼しい小布施や軽井沢や小諸辺りまで。寒い時期は温暖な静岡の熱海とか箱根、御殿場を目指すことが多い。時には群馬の奥の伊香保や沼田市辺りまで足を延ばすこともある。厳冬期はやはり雪道は避けたいので、どうしても県内をウロウロすることが多い。はじめの頃、勝手が分からず旅慣れないぼくは、有名な観光地をピックアップして見学したりしていたのだが、どこに行っても予定調和というかワクワク感に乏しく、さして代わり映えしない光景ばかりなのですぐに飽きてしまった。それに(自分のことは棚に上げて言うのだが)時間と余裕もあるリタイアした年配者たちを必ず大勢見かけるので、せっかくの旅行なのに何とも心が弾まない。
気がつくとぼくの関心は次第に自然に向けられるようになってきた。かといって別に山歩きやトレッキングに夢中になったわけではない。たまにはその真似事をして汗をかいたりもするけれど、むしろ、こんなところにこんな風景があったのかと発見することに楽しみを覚えるようになってきた。不思議な自然の造型美は、またとない旅のご馳走となる。いままで家から離れて知らない土地を眺めてみたいなどと考えたこともなかったぼくは、遅まきながら出かけるようになって、暮らしてきた土地のことはもちろん、日本各地のことなど何も知らなかったなぁ、と痛感させられた。あちこち移動して見たからってそれが何なのだ、それで想像力や空想力が膨らむのか?と問いかけるもうひとりの自分もいるが、やはり移動できる喜び、予期せぬ出会いの喜び、五感で体感できる喜びには抗いがたいものがある。
その最たるものが各地に点在する神社である。当初、騒々しい観光地から逃げ出すように向かったのが神社だったが、そのうち事前に探した神社を目指すことが増えてきた。中でも長野の諏訪湖周辺4か所にある諏訪大社は全国に約25,000社もある諏訪神社の総本社だけあって堂々と風格ある佇まいだが、他にもなかなか味わい深い神社が数多く点在している。
まずはお膝元から。山梨県北杜市白州白須の甲斐駒ヶ岳神社はここが甲斐駒ケ岳登山の起点となるため、多くのハイカーが集う場所でもある。ほとんどの神社は杉の大木茂る清浄閑静な森に鎮座しているが、この神域の森もなかなかのもの。本社は今からさかのぼること約280年前に駒ヶ岳講信者によって建立され、その駒ヶ岳講は地元はもとより京浜、阪神地区にまでも広がる多くの講社によって結成されたのだそうだ。活動が最も盛んだったのは江戸時代末期。それから現在にいたるまで、随所に建立されている数多の石碑などからは往時の篤い信仰の跡がうかがわれる。甲斐駒ヶ岳山頂の奥宮に対して、ここは前宮(里宮)と位置付けられていて、境内を抜けると尾白川にかかる吊り橋があり、黒戸尾根登山道へと続いている。ちなみに尾白川は、建御雷神から生まれた天津速駒と言う白馬が住んでいたことに由来し、この白馬の尾から名付けられたとされているが、夏期に訪れた際には吊り橋付近の渓流沿いは涼を求める多くの家族連れで賑わっていた。
日本では甲斐駒ヶ岳のように山岳信仰の対象となる山が摩利支天と呼ばれている場合があるそうで、道理でこの神社にも摩利支天の文字が各所に点在している。摩利支天の原語は太陽や月の光を意味し、陽炎を神格化したものだそうだ。また、甲斐駒ヶ岳神社の主祭神は「だいこくさま」とよばれている大己貴神(おおなむちのかみ・大国主神)。こうした背景もあってか境内の霊神碑、石碑、石像は、どれも活力がみなぎっていてバラエティーに富み、時にユーモラスでさえある。神社から受ける全体感からは信仰と向き合う真摯さや、白衣を着て鈴振りながら登拝する先達や行者、講員たちのエネルギーが伝わってくるのだが、その本社の一角にひっそりと糸のように細く落ちる滝がある。神域とされている空間なのだそうだ。これは勝手な想像だが、この神域は本社が建立される際の基点となっていたのではないだろうか。うまく伝えられないが、この水の神域にはそう思わせる人知を超えた自然のもたらす地のエネルギーの波動が満ちていた。
他にも山梨には思い出深い神社がたくさんある。永正16年(1519年)に本殿が武田信虎によって造営された、山梨市に在る大井俣窪八幡神社(通称、窪八幡神社)。そして南アルプス市高尾にあるのは高尾穂見(ほみ)神社。来歴は古く、平安時代の書物「延喜式神名帳」に穂見神社として名前を残し、集落の北から林道を進む標高850mの櫛形山中腹に鎮座している。この地に稲作が伝えられた弥生時代に建立されたと覚しき穂見を名乗る神社が櫛形山地を囲む一帯には何社も点在しているが、この立派な拝殿やひときわ目を惹く神楽殿は山中の神社の中で群を抜いている。商売繁盛や養蚕の神社として県内外に広く知られ、甲斐駒ヶ岳神社同様、東京や長野など遠方にも高尾講が存在している。2016年の2月、山梨の大学で開催された講演会を終えた中沢新一さんと初めて訪れてから、その後何度か足を運んでいるが、神社に残る寄進帳を見ると諏訪の人物がたいへん多く、昔から諏訪とこの櫛形とは深い交流が結ばれていたことがうかがわれる。現在も上今諏訪など諏訪を含む地名が多く残り、諏訪の御柱祭に較べればいささか小規模ではあるが、同じ7年サイクルで櫛形でも御柱祭が執り行われている。
ところで今年7月に放映されたNHKスペシャル 「 列島誕生 ジオ・ジャパン 奇跡の島は山国となった」はとても印象的な内容だった。日本列島の成り立ちを描くドキュメンタリー番組で、島国にして山国という奇跡の大地はどんなドラマを経て今の姿となったのかという3000万年に及ぶ奇跡の島の誕生物語だ。ユーラシア大陸の極東で引き裂かれる地殻変動が発生し、大陸に低地が出来始めた。そして1500万年前には日本海となる大きな窪みが形成されたが、この時点では日本列島の原型はまだ関東を境に南北に分離された状態だった。この二つを接続したのは、太平洋プレートに南から進入してきたフィリピンプレートによって引きおこされた海底火山の爆発によるもので、何と奇跡的に一直線上に連続的に発生したことによって偶然もたらされたものだという。こうして分離された大地の間にまず進入してきたのが櫛形山系、次に御坂山系、そして丹沢山系と次々と玉突き状態で進入して、一つの日本列島の原形が形成された。つまり、櫛形はこのような雄大な地質の歴史を背負った地域だったのだ。
では、隣りに位置する御坂山系にはどんな神社があるのだろうか。ぼくのお気に入りは「ブッポウソウ」と啼くコノハズクが確認された地として有名な檜峯(ひみね)神社だ。御坂町上黒駒から神座山林道という林道へと入り、「檜峯」の由来となったヒノキ林に囲まれた山道をおよそ4kmほど進むと檜峯神社へとたどり着く。標高約1100mの社殿奥には御神木である推定樹齢300年以上の御神木の大杉が立ち、その雄大な姿は生命力を湛えて神々しい。御坂山系の鬱蒼とした巨木林の深い静寂に包み込まれた神社の社殿一帯には、さながら神々の庭といった趣きがある。
長野にも多くの神社が点在しているが思わぬ所にひっそりを存在する神社があったりして、この地の懐の深さを実感させられる。初夏のある日、蓼科からの帰り道で茅野市を移動中に道路脇に立つ欅だろうか、大木が目に入り呼び止められた気がして車を停め、その先に目をやると潺(せせらぎ)を跨ぎ、林へと誘うように続く狭い石段の先に石鳥居が見える。さっそく石段を下るように歩を進め、さらにその奥にある「天照大神宮」と記された質素な木製鳥居をくぐるとやっと神社が見えてきた。茅野市芹沢地区にあるこの神社は諏訪大社の小宮の一社である木戸口神社とよばれている。小さな祠を中心にして境内の四隅には御柱が立っていたが、印象的だったのは石の小祠に丸石が納まっていたことだった。男女像を彫り込んだ双体道祖神の多い長野で丸石を発見することはあまりないから、これにはちょっと驚いた。この神祠境内には数本の小川が流れているので、水の神社といった趣きもある。一番大きな裏側の小川は乙女滝に繋がっているのだそうだ。大木に誘われるように偶然こんな神社に出会うと、なんだか得したような気持ちになる。これも旅の小さな贈り物と言えるだろう。
さて近県の群馬まで足を延ばすと、またひと味違う神社もある。今年初秋に訪れたのは群馬県高崎にある榛名(はるな)神社。榛名湖から10分ほど山道を進むと樹林の先にある榛名川のせせらぎに沿うように参道入口が見えてくる。ここは関東屈指のパワースポットと言われてるそうだが、なるほど足を踏み入れた途端に辺りに点在する奇岩や古木の奇景には圧倒される。榛名神社の歴史は古く、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられている。御祭神が祀られてた御姿岩の洞窟や武田信玄が箕輪城攻略の際に矢を立て戦勝を祈願したとされる矢立杉は国の天然記念物となっている。そしてその奥に立つ、本社・幣殿・拝殿、国祖社・額殿、神楽殿、双龍門、神幸殿、随神門の 6棟計は国の重要文化財となっている。まさに大地のエネルギーがみなぎる堂々たる風格を有する神社といった印象だった。
ほとんど神社はレベルの差こそあれ、こんな場所にこそ神社を構えなければと思わせるようなロケーションに建っているケースが多い。はじまりは1本の大木だったのかもしれない。御神木とも称される木々は古神道における神体のことで、神域の意味も同時に内包するとされている。つまり、実は自然が神社誕生の必然を用意しているわけで、人間はそれを感受して造営に向け行動を起こしたのだろう
最後にもっとも記憶に留めておきたい神社のお話。山梨には山里の温泉がたくさんあるが、古くから湯治場として栄えた下部温泉はぼくが小学生の頃に盲腸の術後に祖母とともに湯治(とうじ)に訪れ、数日過ごした思い出の温泉でもある。ふと思いたち、半世紀ぶりに訪れてみると今はもうすっかり寂れてしまい往時の面影はない。翌日気落ちして宿を後にする際に、せっかくここまで来たのだから国指定重要文化財になっている門西家(もんざいけ)住宅に行ってみようと思いついた。細くくねった下部温泉街の道を上り、更に山道を進んだところに湯之奥という集落がある。ここに建つのが江戸初期の入母屋造りの旧家、門西家住宅だ。湯之奥金山や山林管理などをして、湯之奥村名主や関守を代々つとめてきたのが家主だという。比較的コンパクトな民家建築といった印象なので肩すかしを食ったような気がしたが、徒歩でさらにその先の細い坂道を登って行くと、急な沢に落ち込む手前のウラジロガシ群生の中に集落の最奥部に思いがけなくひっそりと鎮座する神社が見えてきた。朽ち果てた状態で検索してもまったく情報はないが、どうやら「湯の奥山神社」と呼ばれていたようだ。ここから先はすべてが深い沢に呑み込まれる、そんな結界のような場所にその痕跡をとどめ忘れ去られた神社は、今も強い霊性の磁場に包み込まれていた。すくなくともぼくにはそのように感じられた。沢を隔てた隣りには、日蓮宗総本山である身延山久遠寺が建つ身延山がそびえている。日蓮がインドの霊鷲山に見立てて信仰の山として位置づけたとされている身延山だが、霊性の磁場としては、この湯の奥山神社だって少しも引けは取らないのではないだろうか。神社は磁場の目印に過ぎず、その奥には絶えず自然から湧き上がってくるものがある。そして片時も絶えることなく脈々とスピリチュアリティがそこには流れ続けているのだと神社は語りかけてくる。

吉田のうどんと格差問題
12年ほど前のある時期、ぼくは知人のTさんと往復書簡もどきメールを交換しあっていた。Tさんは高校の2年先輩にあたる人で、大学卒業後の出版社勤務を経て、100年近く続く実家の家業を引き継ぐために山梨に戻ってきた。40年ほど前のことだった。精力的に県内観光業界の牽引役として活躍してきたTさんは、ある時自身の店舗で販売する土産品に満足できないからと、オリジナル商品の開発を思いたった。それから単独土産品店としては例を見ないほど多くのPB商品を企画開発していくのだが、ぼくはその時期にTさんと引き合わされる機会があって、一手にデザインを託されることになった。
ぼくらには多くの共通点があったのだが、ぼくに持ち合わせていなかった能力をTさんは持っていた。Tさんは何事にも興味を示すと、抜群の理解力を発揮して「難しく考えることはない。簡単なことだよ」と言ってはすぐにマスターしてしまう。そんな人並み外れた集中力や実行力を持っていた。それは典型的なお旦那気質といえるものだった。しかし、弱点は多くの旦那衆がそうであるように、達成した途端に飽きてしまい、次の対象に興味を移してしまうことだった。それはそれでフレキシブルであるともいえるし、事業を展開していく上では、その気質が有利に働くこともある。
逆に生来不器用な人はどうだろう。別に法則があるとは思わないが、道を究めたと評される人物は、往々にして出だしにおいてつまずくケースが多いような気がする。絶望的なほど不器用だったり、呑み込みが悪かったり、とにかくなかなか順調とはほど遠い滑り出しにもかかわらず、粘り強く高い志に向かう牛歩の歩みから次第に輝きを増してきたりする。持って生まれたこうした気質によって、その後の人生の歩み方が別れていくということが多々あるようだ。
その後、日本の観光業は時代意識や購買意識の変化によって大きく変革を余儀なくされていくことになった。やむなくTさんは、マスターした蕎麦打ちを活かして、その地域に伝わる伝統料理を継承する蕎麦屋を開店し、蕎麦打ち道場も主宰して、家業を土産品店から徐々にシフトしていくことにした。往復書簡は丁度そんな時期に交わされたものだった。以下の抜粋は、他愛もないうどん談義から格差問題へとテーマを移しながら、当時のぼくらの変化に対する戸惑いや考察が反映されている。
〈食後感想文〉
ごぶさたをしています。気がつけば、季節はすでに春から初夏へと移ろい、日々の流れに翻弄される我が身を憂える今日この頃であります。
ところで先日、甲斐絹に関する仕事で富士吉田に行った折、昼食にと誘われ、当地の繁盛店と誉れ高い「うどん屋」に連れていってもらいました。江戸末期から昭和にかけてこの郡内地方の基幹産業は養蚕や機織りでしたが、その担い手となっていた忙しい女性に代わって炊事を受け持った男性たちが強い力で地粉をこねて打ったのが、コシ、硬さ、太さを特徴とする吉田のうどんの始まりだと言われてますね。
着けばびっくり、入口には10人ほど入店待ちの行列が。駐車しているナンバーをチェックすると半数以上は近県のものでした。これは期待できるぞと、はやる心を抑えてテーブルにつきました。地元の人は最低2品頼むものだと同行者に促され、ぼくは「つけうどん」と「肉うどん」を注文。(「肉うどん」、吉田では馬肉です。細かなバラ肉が申し訳程度脇に添えられているのです。)麺の硬さは吉田としては平均的なものだそうですが、食感は正直言って相当な固さです。すいとんの長い棒をきざみキャベツと一緒に噛みしめながら、これは一種の苦行だと思いました。悪戦苦闘するぼくが食べ終えるのを待ちきれず、連れ達はさらにもう1品追加注文するではありませんか。もう、信じられません。唯一こだわりを感じたのは、お店が独自にブレンドしたという七味唐辛子だけでした。
それにしてもまったくこんな食べ物に、行列してまで群がる現象を一体どう理解したらいいのでしょう。これからやって来る総低収入化社会に備えてのサバイバル・トレーニングか、はたまた幼年期の恒常的な粗食生活へのノスタルジーなのか、謎は尽きません。まぁ、行列といっても、狭い店内の非効率なテーブル配置やうどんが無くなり次第商い終了の3時間という営業時間を考えたら、さほど驚くこともありませんが…。甲州はいろんな意味で本当に貧しい地域なのですね。その貧しさを逆手にとって、しぶとく商売にしてしまうのも甲州人特有の智恵なのでしょう。バブルを潜り抜けてきた日本人には、貧しさだって今や立派なトレンドなのかも知れません。今の自分たちを支えているバックボーンは、実はこうした貧しさなんだと実感するために、時折長いすいとん棒と格闘するのも、それはそれで意味ある行為と言えなくもありません。逆説でなく、貧しさの中に新種の豊かさを発見しなくてはならない時代になってきたのだと思います。Tさん、このあたりにこれからの商売を切り開いていく鍵が秘められているような気がするのですが、いかがなものでしょう。
〈Tさんからの返信〉
「貧しさの中から新種の豊かさを発見する」。確かにそうともいえます。しかしながら、貧しい人たちを相手に商売として成功するには、かなりの規模とボリュームが必要となり、したがって資本力が必要となるのではないでしょうか。つまり、一億総中流意識から、じわじわと富めるものと貧困層の二極化の傾向を感じます。
これもアメリカを手本としてきた日本経済の当然の帰結かもしれません。あくまでも経済的な豊かさを追求したい人と、あきらめながら貧しさの中に言い訳のように精神的な豊かさを求める人たちです。自分がどちらに属するのかは言うまでもありませんが、下手をすると大貧民になりかねない現在の経済環境の中、小金をしっかり抱いて、生きている間、飢えることの無いように願うばかりです。これが凡人の考え方であり、このような人たちを相手に大もうけできる人は、一握りの大金持ちなのでしょう。不思議なことに、お金はお金が大好きで、磁石に吸い寄せられるように大金持ちの所に吸い寄せられて行きます。まとまったお金を持っている人には、金利でさえも10%ぐらいは稼げる経済環境です。 10億円で年間1億円 20%税金を払っても8.000万の収入です。一方1.000万程度では0.01%の金利を稼ぐのもやっとです。
こんな時代では、まともに働いて収入の無いときに備えることなどできるはずもありません。若者に勤勉な労働を期待することも出来ず、刹那的な生き方をとがめることも出来ません。いっそのこと、階級制度で一攫千金が実現不可能な社会を選択したほうが幸福感を得やすいのかも知れません。誰もがビルゲイツになれる可能性を持つ時代のほうが多くの不幸をもたらすことになるのではと考えたりします。最善でも金持ち層から少しでも掠め取るべく、スキルを積み上げて小規模な展開しか出来ないのがほとんどの小商売人の行く末ではないでしょうか。深く考えず、刹那的な幸福感が少しでも続けば良いと考えられる人たちは幸せです。そういう幸せな人になれればとも思います。
〈再びTさんへの返信〉
懲りもせず、また返事を書こうとしているぼくは、たぶん暇なのです。今日いっぱいまでは、かなり呑気なのです。忙しいTさんは律義にこんなぼくにつきあう必要ありませんからご一読後はどうぞ忘却の彼方へとご出発ください。
おっしゃるように、このまま貧富二極化の流れがさらに加速されていくことは必至ですね。貧困層を餌にしながら資産家は肥大し続け、膨大な数にのぼる貧民が、一握りの大金持ちを支えていくような経済システムは益々強固なものとなっていくでしょう。貧困層全域に疫病のように蔓延する絶望と諦観。考え得る貧困層の抵抗など、それこそ富裕層の想定範囲内にすっぽりと収まるような限定的なものでしかないといった、市場世界はまさに出口なしの絶望的状況です。
さらに、こうした強固な経済システムが送り出してくる商品や仕事が人々の暮らしそのものを壊していることも事実です。「仕事が暮らしを壊す」。高度成長期に誰がこんなことを想像したでしょう。勤勉な日々の集積の結果が、自らを絶望的に貶める強固な経済システムという怪物を育て上げ、壊れた暮らしの中で不安におののく荒廃した諦観しか残すことができなかったとは…。「豊かな物質に囲まれた貧しい心」にまつわるお題目は、経済システムの周囲を堂々めぐりしながら「だからといってどうしようもないじゃん」化石となって思考を鈍化させるか停止させようとしています。金持ちが幸せなのか不幸なのかなんてまったくぼくの想定外だし、知ったこっちゃないのですが、いかにこの息苦しい世界が人間の想像力を破壊してしまっているのか、日々の報道から絶え間なくぼくらに向かってこうした現実が突きつけられてきます。もはやぼくたちの現代が何を失ってきたのかは、はっきりしています。
先日(2005年4月16日)、出演先の北海道で急死してしまったミュージシャンの高田渡さんがつくった曲があります。広場で並んで腰かけ息子に語りかける「漣(れん)」という曲です。(「漣」は彼の息子の本名です)
『漣(れん)』
漣とぼくは居る
二人で居る
野原に座って居る
空を見上げて居る
「見えるものは みんな人のものだよ」
「うん」と漣は言う
親のぼくも頭が悪いが、どうやら息子も似ているらしい
「見えないものは みんなぼくらのものだよ」
「うん」
「腹減ったか?」
「腹減った」
(Fishin’on sunday の収録曲で、中川イサトのアコギ演奏をバックに、高田渡がボソボソと朗読している)
貧乏人で頭の弱い父親が息子に語りかけます。「見えるものはみんな人のものだよ。見えないものはみーんな、ぼくらのものだよ。」神様は想像力をちゃんと貧乏人のために残しておいてくれたのです。そんなの負け犬の言いわけだ、となじる人もいるでしょう。でも、想像力がお金で買えるわけではありませんよね。市場経済の合理性からは決して生まれることのない、個別性に満たされたものは確かに存在し得る。想像力によって結びつけられた関係性の中で成立する商品というものだってあるはずです。それがぼくは「貧しさの中の新種の豊かさ」なのだと思うのです。でも、これって少しも新しいことなどではないのですね。今や手のつけられないモンスターに成長を遂げてしまった経済システムが、数値化することのできない貧しさの中に息を殺して潜んでいた豊かさを、一周した「新しさ」へと押し上げているだけなのかもしれません。個人として、この世界がつくられている常識に従って生きる必要はない。そう考える人が一人づつ増えていけば、いつかいつか世界は変わっていく。楽観的にそう信じたいものです。
*
さて、それから12年後のぼくらはといえば、「加齢」は間違いなく忍び寄ってきてはいるものの、いまだ「枯れて」はおらず、「侘び」、「寂び」とも無縁。相変わらずぼくの仕事は、de(前に=未知の=見えないもの)sign(しるすこと=形を与える)。「見えないものは、みんなぼくのものか?」。それを可能にする想像力がはたして心のどこかにまだ残っているのか、自問の日々は続く。

ハンブルグのコンサートホール
2017年1月11日、ドイツ・ハンブルグのエルベ川の運河沿いに完成したコンサートホールで、こけら落としの演奏会が開催された。オケはこのホールを本拠にする「NDR エルプフィルハーモニー(NDR Elbphilharmonie Orchestra、旧称:北ドイツ放送交響楽団)」。首席指揮者はトーマス・ヘンゲルブロック。やがて演奏が始まるのを固唾を呑んで待つ観客の耳に流れてきたのは、上階観客席の通路に立ったオーボエ奏者カレフ・ユリウスの奏でる「オウイデイウスによる6つの変容」から「パン(ブリテン)」のメロディ。ホール全体に響き渡る澄んだ音色はやがて糸を引くように遠ざかり、ふくよかなオーケストラの楽曲「瞬間の神秘」から「呼びかけ、エコー、プリズム(デュティユー)」へと引き継がれていく。続く3曲目は客席の中に立つ、世界中から絶賛されるカンターテナー歌手・フィリップ・ジャルスキーの歌声にバトンタッチされていく。傍らで伴奏するのはハープのマグレート・ケール。「ラ・ペツレルリーナ」からの楽曲は「高き天球から(カヴァリエーリ/アルキレイ)」。
*
私は いと 高き天球から来た
いと 高き 天球から来た
美しい歌声のセイレーンに付き添われ
私の名はハルモニア
人である汝らの元に降りてきた
翼を羽ばたかせ 火災が天に昇る
*
このようにコンサートは、客席から奏でる音楽とステージで奏でるオーケストラの音楽とが交互に、ときに静かに、ときに高らかに、あたかも会話するかのように進行していく。外では楽曲に合わせてカラフルなイメージパターンが、暗闇に浮かび上がるように建物の外壁に最新技術プロジェクションマッピング(Projection Mapping)によって投影されている。ハンブルグのランドマークとして計画され、2007年の着工から9年の歳月を経てやっと完成した「エルプフィルハーモニー・ハンブルク(Elbphilharmonie Hamburg)」はその夜、ホールは音楽の命が吹き込まれる瞬間を迎えていた。
今年5月1日に放映されたNHK BSプレミアムシアター ドキュメンタリー「エルプフィルハーモニー」。このホールが様々な苦難を乗り越えながらも完成までに漕ぎ着ける過程と、晴れやかなお披露目コンサートの模様が合計4時間にわたって紹介された。ボタンの掛け違いから発生する膨大な無駄な時間と経費。意見の対立や反目。世界最高水準のホールを誕生させる巨大プロジェクトに対して生み出される悪意と、それを凌駕する多くの善意と情熱。ドイツ文化の奥深さが伝わってくる4時間だった。
2007年にハンブルグ市は、運河沿いに建つ倉庫の歴史ある外壁は残し、内部を完全撤去して、そこに観客がオケと指揮者を囲むように座るコンサートホールの建築を計画した。建物設計を担当したのは、プリツカー賞をはじめ数々の賞を重ね、2000年のテート・モダン、2003年の東京・プラダ青山店、2008年の北京国家体育場(通称「鳥の巣」)などで世界から注目を浴びているスイス・バーゼルのヘルツォーク&ド・ムーロン( Herzog & de Meuron)。そもそもこの番組を見たのも、以前からこの建築家ユニットに興味を持っていたからだった。そして最高水準のホール作りを託されたのはウィーンから招かれた音楽ホール総監督・クリストフ・リーベン・ゾイッター。さらにホール水準の要となる音響を任されたのは、日本人の音響設計家で永田音響設計所属の豊田泰久。
まず、この建物を強く印象づけるのは王冠を連想させる屋根のシルエットだ。そして下には湾曲した1,000枚以上の1枚50,000ユーロの窓からなる美しいガラス壁が連なるシルエットを支えている。ガラスは様々な耐久テストが繰り返され、5ヶ所の共同作業によって製作された。各層ごとにコーティングされて最終的には4層になる。建物内の温度上昇を抑える遮光層。500パターンの水玉模様を組み合わせるため、すべての窓が違う模様になり、一番外側の層にはクロームメッキを施して、建物が船のレーダーを反射するように配慮された。こうしてガラスは完成するまでにドイツ国内を7回移動を繰り返し、工程の最後にはイタリアのパドバにある特注かまどで焼かれ、波状に曲げられる。複雑なガラスの層を痛めずに曲げられるのはこの会社の技術しかなかった。こうして時間とお金をかけた世界に一つしかない、トータル5,000トン以上もある1,100枚の異なる窓でできたガラス壁が用意された。
しかし、良いものは高くつく。次第に膨らみ続ける建築費用。綿密に組み上げられた8,000トンの屋根を支える鉄骨だったが、その組み方は建設の不安材料となった。社内の検証結果と異なると、2011年に建設会社は屋根の構造が力学的に安全でないことを理由に工事を中止する。本当にそうなのか、それとも施工費をつり上げるためなのか、議論は激化した。設計者と建築会社は互いにその責任をなすり合い、やがて好意的だった市民の目も次第に厳しくなる。工事現場の周りでは抗議集会が開かれる日もあった。中止に伴う経費の増大で財政難に陥った市は、市立病院を複数売却するがそれでも足りず、ホールの予算や完成の日程はあいまいとなっていく。そこで市議会の調査委員会は20人の証人喚問を行った。その結果明らかになったトラブルの原因は、建築会社と設計者がそれぞれ別々に市と契約したことによる複雑な契約関係と早期の公示や市の管理が行き届かなかったことにあると判明。市は契約した建設会社を見限って独自に工事を進めるか、裁判を続けるか検討を重ね、いよいよ2012年12月、建物の将来を決める時がきた。建築会社は契約の抜本的な見直しと、2億ユーロの上乗せを条件に工事の再開を申し出ていたのだ。結局、市は和解の道を選んだが、その代償は高くついた。前市長時代の2009年の初見積りの建設コストは、現市長の2013年には10倍にまで膨らんでしまった。総額7億8,900万ユーロ。
ともあれ、工事はなんとか再開された。残るは大ホール。新旧の建物の間には公共広場“プラザ”が設けられ、公演中には汽笛が聞こえたり、併設ホテルや住宅に音が響いたりしないようにしなくてはならない。その解決策は「浮き床工法」。ホール全体を二重構造にして床下にスプリングを入れるとホールは浮いた形となり完全に遮音される。
ホールの要となる音響設計を担当した豊田チームの残響目標はわずか2秒だった。そこで、天井には“白い皮膚”と呼ばれる反響板が設置されることになる。建築家のヘルツォークは死者を連想させる“白い皮膚”という呼び名を嫌い、これは化石化した甲殻類だと主張する。主原料はバイエルン地方の石切場でとれる石膏を磨り潰し、古紙を混ぜて溶かして固めた板状の石膏板だ。表面を固くしすぎるとエコーが出てしまう。逆に吸収がよすぎると音がこもってしまう。適正な固さとなった石膏板は1枚づつドリルで建物の屋根と同じ波模様に彫り込まれて、1万枚の石膏板が巨大モザイクを作り出す。歴史的な音楽ホールの天井や壁には美しい彫刻や装飾が施されている事が多いが、それで音が分散されて響きが柔らかくなるからなのだ。こうして何ヶ月もかけて天井に取り付けられたパネルの総重量は1,800トンで大型旅客機3機分の重さになる。また、座席と観客はホールで音を最も吸収する要素となるため、客席の音響テストが参加者を集めてイタリアのリミニの研究所で実施された。座面の材質は音響的には硬い方が好ましいが、建築家は座り心地を重視する。豊田はクッションとカバーの間に空気が残っていると音響に影響すると主張し、全ての座席カバーは座面に直貼りされる事になった。2,000席の椅子が設置されて音響の仕事は終了する。ホールの遮音性は高く、音漏れは一切ない。豊田が調整できることはもう何もない。
最後の仕上げは、ガラスの雫でホールを取り囲むこと。通常の電気用の吹きガラスは底が厚くて上部が薄い。しかし照明効果を考えると上部は厚くしたい。上部が厚いガラス玉が成功するのは2つに1つだが、この建築家の要望に応えられる工房があった。通常とは異なるやり方で吹きガラスを作る、エルベ川上流のチェコの山地にある家族経営のガラス工房がホールを照らす光りの雫を丹念に作りあげた。こうして予定から6年遅れの2016年に、やっとホールは完成した。次は演奏家たちがホールに命を吹き込む番だ。
機能もデザインも最高でこそトップクラスのホールと言える。そこで設計には楽員の声が反映された。建築家は楽員から様々な意見や要望を吸い上げ、練習に集中できる楽器ごとの個室や、舞台裏には休憩や調整をする空間を用意した。リハーサルの緊張をほぐし、運河の景色や川や空で楽員の心を癒やす場も建物には組み込まれている。ホールの音響はオケの演奏にダイレクトに影響する。互いの音をよく聞くようになり、ホールの澄んだ響きを身をもって感じた楽員は初リハーサルで自分の出す音に感動して涙した者もいたという。音楽をよく理解できる響き。透明感のある崇高な雰囲気を宿す響きがそこにあった。
一市民の幻想に過ぎなかった町のランドマーク計画は苦難の末に建設され、あらゆる醜聞を退け、建物の心臓は鼓動を始めた。理想、夢、希望、忍耐、熟慮、寛容、喜びが惜しむこと無く注ぎ込まれた、芸術という名の樹木はドイツの大地に文化の根を張り巡らせていく。ステージからはオケとプレトリウス合唱団よる「5声と通奏低音のためのモテット」から「あなたはなんと美しいことか(ヤコプ・プレトリウス)」が流れ出し、澄んだ響きにホールは満たされていく。
*
あなたはなんと美しく麗しいことか
いとしい乙女よ
あなたは歓喜に包まれている
あなたの立姿はまるでシュロの木のよう
あなたの胸はたわわなぶどうの房のよう
行こう いとしい人よ 見に行こう
ぶどう畑に花が咲いているだろうか
もしザクロの花が満開だったら
あなたに心をささげよう
私の心をささげよう
(参考情報:2017年5月1日放映NHK BSプレミアムシアター ドキュメンタリー「エルプフィルハーモニー」ナレーション、スーパー。またオープンに先駆け、先行取材した旅レポブログでもプロジェクトを俯瞰することができる)

別離
4月5日に86歳で亡くなった詩人で評論家の大岡信さんの死を悼んで、故人と親交の篤かった詩人、谷川俊太郎さんの詩が新聞に寄せられていた。
*
大岡信を送る 2017年卯月
本当はヒトの言葉で君を送りたくない
砂浜に寄せては返す波音で
風にそよぐ木々の葉音で
君を送りたい
声と文字に別れを告げて
君はあっさりと意味を後にした
朝露と腐葉土と星々と月の
ヒトの言葉よりも豊かな無言
今朝のこの青空の下で君を送ろう
散り初(そ)める桜の花びらとともに
褪(あ)せない少女の記憶とともに
君を春の寝床に誘(いざな)うものに
その名を知らずに
安んじて君を託そう
(4月11日・朝日新聞)
*
万感の思いを胸に納めて、「言葉よりも豊かな無言」と記す詩人の言葉は波音や葉音、そして桜の花びらに想いを託す。ところで、ぼくは偶然、谷川俊太郎さんと並んで座る機会が一度だけあった。上京し、午後閑散とした地下鉄で移動中、到着した四谷駅で、開いた向かいの扉から小柄な老人が乗り込んできて、ぼくのとなりに腰を下ろした。一瞬見覚えのある顔だなぁと思案して、すぐにそれが谷川俊太郎さんだと思いあたった。ぼくより先に下車するまでのほんの5分足らずの出来事だったが、すっと背筋を伸ばして身じろぎもせず真っ直ぐ前を見据えている年齢を感じさせない佇まいが印象的だった。
昔は「君」と呼べる友のいる安心感があった。叱ってもらえる人がいるという安心感もあった。しかし歳を重ねるにつれ、そうしたかけがえのない人やお世話になった人との別れが次第に現実のものとなってくる。その時、残された者たちは別離とどう向き合うのか。
宮澤賢治に大きな影響を与えた妹トシの死。トシは賢治にとって自分を最も理解してくれる存在であった。妹は彼の心の支えであり、心強い同志でもあり、そこには慕情さえも…。
下の3編は賢治が別れのその日、万感を込めて詠んだ『永訣の朝』と『松の針』、そして『無声慟哭』。その日から賢治は7ヶ月間詩作することはなかった。
*
「永訣の朝」
けふのうちに
とほくへいってしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふっておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゅとてちてけんじゃ ) ※
うすあかくいっそう陰惨な雲から
みぞれはぴちょぴちょふってくる
(あめゆじゅとてちてけんじゃ )
青い蓴菜のもようのついた
これらふたつのかけた陶椀に
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたくしはまがったてっぽうだまのやうに
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゅとてちてけんじゃ )
蒼鉛いろの暗い雲から
みぞれはびちょびちょ沈んでくる
ああとし子
死ぬといういまごろになって
わたくしをいっしょうあかるくするため
こんなさっぱりした雪のひとわんを
おまへはわたくしにたのんだのだ
銀河や太陽 気圏などとよばれたせかいの
そらからおちた雪のさいごのひとわんを・・・・・・
「松の針」
さっきのみぞれをとってきた
あのきれいな松のえだだよ
おお おまへはまるでとびつくやうに
そのみどりの葉にあつい頬をあてる
そんな植物性の青い針のなかに
はげしく頬を刺させることは
むさぼるやうにさへすることは
どんなにわたくしたちをおどろかすことか
そんなにまでもおまへは林へ行きたかったのだ
おまへがあんなにねつに燃され
あせやいたみでもだえてゐるとき
わたくしは日のてるとこでたのしくはたらいたり
ほかのひとのことをかんがへながら森をあるいてゐた
《ああいい さっぱりした
まるで林のながさ来たよだ》 ※
鳥のやうに栗鼠りすのやうに
おまへは林をしたってゐた
どんなにわたくしがうらやましかったらう
ああけふのうちにとほくへさらうとするいもうとよ
ほんたうにおまへはひとりでいかうとするか
わたくしにいっしょに行けとたのんでくれ
泣いてわたくしにさう言ってくれ
おまへの頬の けれども
なんといふけふのうつくしさよ
わたくしは緑のかやのうへのも
この新鮮な松のえだをおかう
いまに雫もおちるだらうし
そら
さわやかな
terpentine (ターペンタイン)の匂もするだらう
「無声慟哭」
こんなにみんなにみまもられながら
おまえはまだここでくるしまなければならないのか
ああ巨きな信のちからからことさらにはなれ
また純粋やちひさな徳性のかずをうしなひ
わたくしが青ぐらい修羅をあるいてゐるとき
おまえはじぶんにさだめられたみちを
ひとりさびしく往かうとするか
信仰を一つにするたったひとりのみちづれのわたくしが
あかるくつめたい精進のみちからかなしくつかれてゐて
毒草や蛍光菌のくらい野原をただよふとき
おまへはひとりでどこへ行こうとするのだ
(おら おかないふうしてらべ) ※
何といふあきらめたやうな悲痛なわらひやうをしながら
またわたくしのどんなちひさな表情も
けっして見遁さないやうにしながら
おまへはけなげに母に訊くのだ
(うんにゃ ずゐぶん立派だぢゃい けふはほんとに立派だぢゃい)
ほんたうにさうだ
髪だっていっそうくろいし
まるでこどもの苹果(りんご)の頬だ
どうかきれいな頬をして
あたらしく天にうまれてくれ
(それでもからだくさぇがべ) ※
(うんにゃ いっこう)
ほんたうにそんなことはない
かへってここはなつののはらの
ちひさな白い花の匂でいっぱいだから
ただわたしはそれをいま言へないのだ
(わたくしは修羅をあるいてゐるのだから)
わたくしのかなしさうな眼をしてゐるのは
わたくしのふたつのこころをみつめてゐるためだ
ああそんなに
かなしく眼をそらしてはいけない
註
※あめゆきとってきてください
※ああいい さっぱりした
まるではやしのなかにきたやうだ
※あたしこわいふうをしているでせう
※それでもわるいにほひでせう
*
エリック・クラプトンは最愛の息子コナー(享年4才)を転落事故で亡くした。打ちのめされた日々を送る彼は、その深い悲しみや苦しみと向き合うために音楽に救いを求める。そして生まれたのがあの名曲『Tears in Heaven』だったことはよく知られている。クラプトンはここで(Eric Clapton – Tears in Heaven live Crossroads 2013)歌われているように、コナーの死後12年の時を経て、やっと『Tears in Heaven』の演奏を封印することができたのだった。
*
Would you know my name if I saw you in heaven?
Would it be the same if I saw you in heaven?
I must be strong and carry on.
‘Cause I know I don’t belong here in heaven.’
父さんの名前覚えてるかな?
もし君の居る天国で会ったとしてもね
前と同じようにしてられるかな?
もし君の居る天国で会ったとしたらさ
父さん強くならなくっちゃいけないな
それを続けて行かなくっちゃ
分かってるよ 父さんの居場所
天国じゃないって事はね
*
人の悼み方はさまざまである。最後にもう一つ。
去る2016年3月2日投稿ブログで、2015年10月23日に急逝した友人のデザイナー、西野洋さんのことを書いたが、その後、彼と交流の深かった人々の中から自然発生的に作品集制作の話が持ち上がり、制作委員会に10名のデザイナーが参加することとなった。彼の残した思索や活動の軌跡を次の時代に結びつけようと、残された資料を整理・分類しながら分担して紹介する作業は、それから半年以上に及んだ。この小さなプロジェクトは、彼の思考や造形と向き合う貴重な時間を与えてくれたし、結果的にぼくらを再び繋げてくれた。名を連ねるぼくも、西野洋さんのスモールグラフィックを紹介する頁を担当したのだが、東京以外の地域で活動するメンバーはドイツのBaumann & Baumannさんらとぼくだけだったので、実質的な制作作業は美登英利さんと白井敬尚さんを中心に東京のメンバーが担ってくれた。
こうして生まれた一冊の書物は「西野洋 思考と形象(Hiroshi Nishino Philosophy and Design)」と名付けられ、デザインを生業とするものならではの追悼のかたちとなった。ゆかりのあったデザイナーたちへとバラバラに散っていた西野さんの思考と形象の記憶は、再びこの書物の中で統合され、再構築されることになる。そうして、それら記憶と記録の集合体は、彼がもっとも愛した書物という偲びの場で束の間の再生を果たすことが出来たのだと思う。
最後に、ぼくの好きなお別れの歌をご紹介。NHK BSで放送されていた「名探偵モンク」が最終回を迎えたが、そのエンディングでしみじみと流れていた、ランディ・ニューマン(Randy Newman)の「日々のこと(When i’m gone)」。 (※英歌詞付き動画なので、以下は和訳のみ)
*
「When I’m Gone」
Randy Newman
一生迎えたくなかった
お別れの時がすぐそこ
悲しむ人がいても 先へ進まないと
寂しがるのは 分かってるけど
出会ったとき 私はボロボロで
思い出すより 忘れたいことばかり
闇を抜けるまで 見届けてくれた君
寂しがるのは 分かってるけど
控え目な男だから こういうのは苦手
でも支えてもらった せめてものお礼に
お別れでなく “またね”と言おう
私に向けた光は どうか消さないで
君がいたから 私は強く成長できた
寂しがるのは 分かってるけど
君がいたから 私は強く成長できた
寂しくなるのは きっと私のほう
寂しくなるのは 間違い無く私
